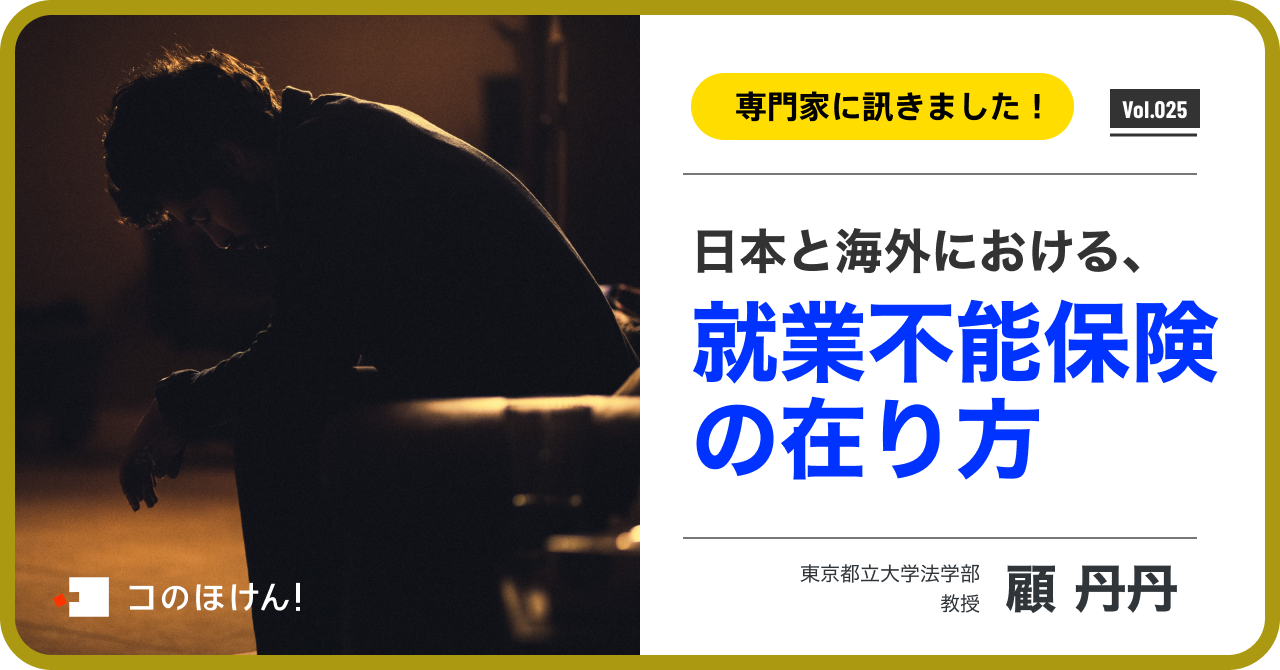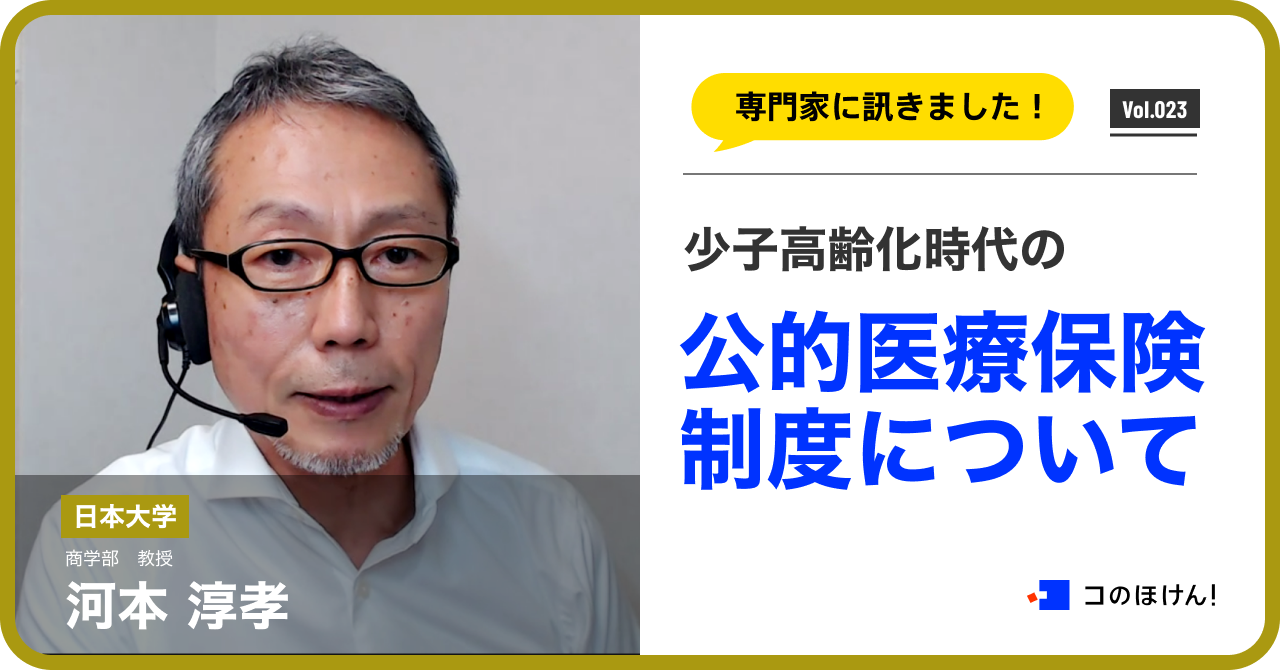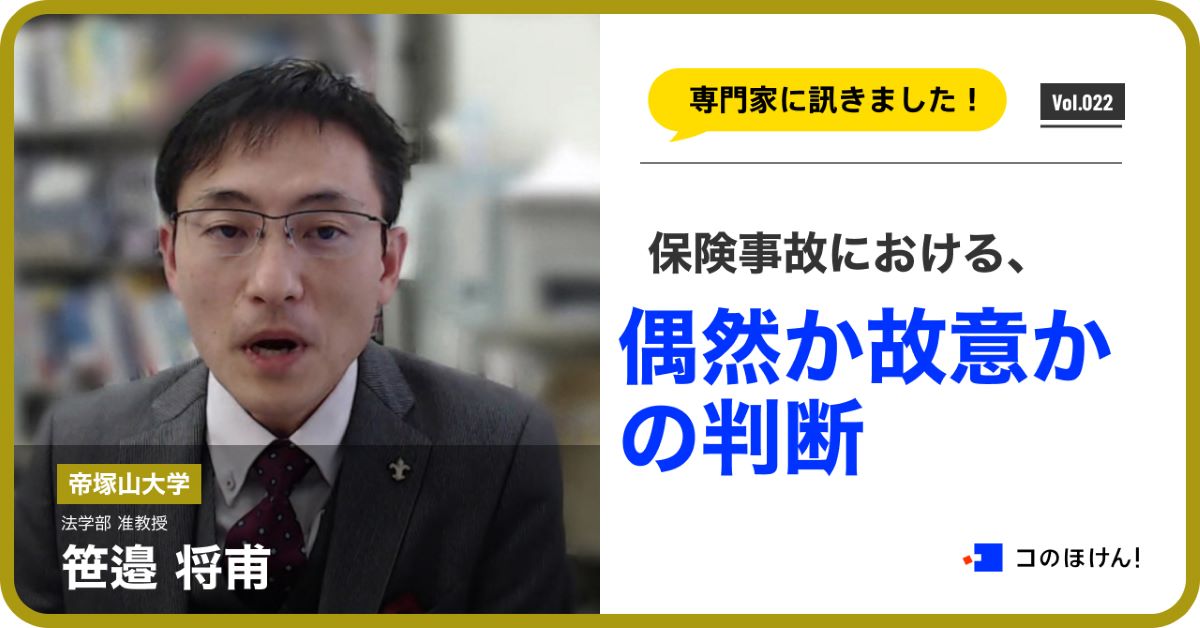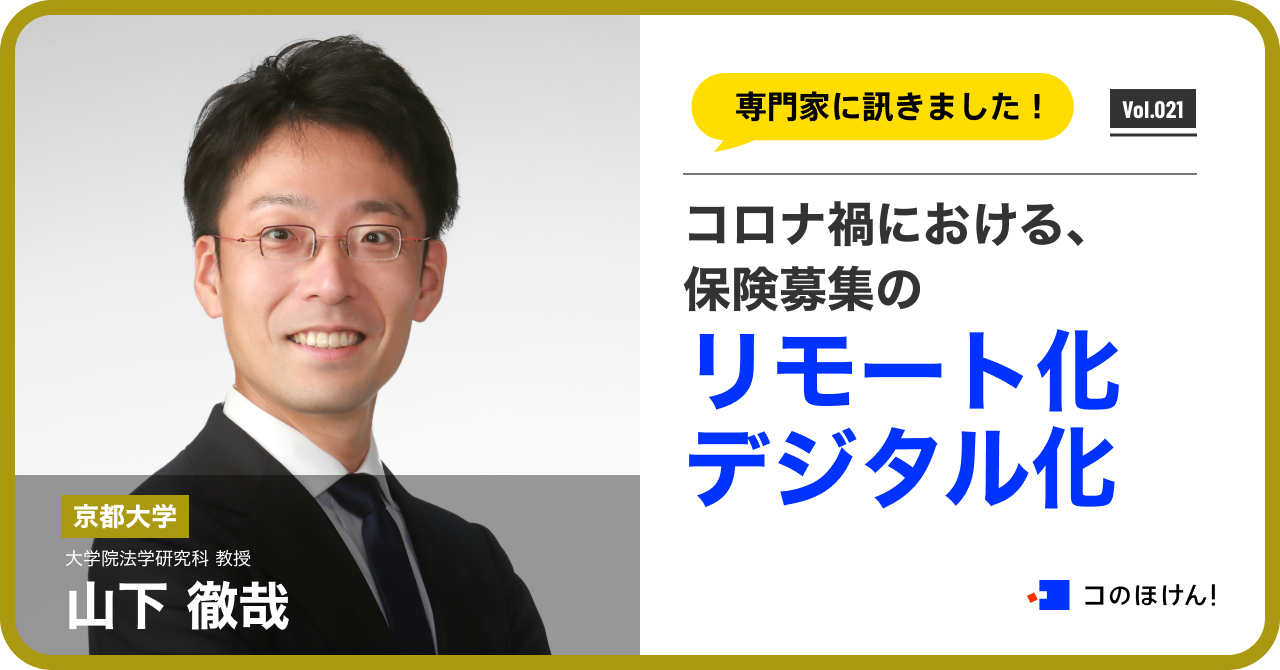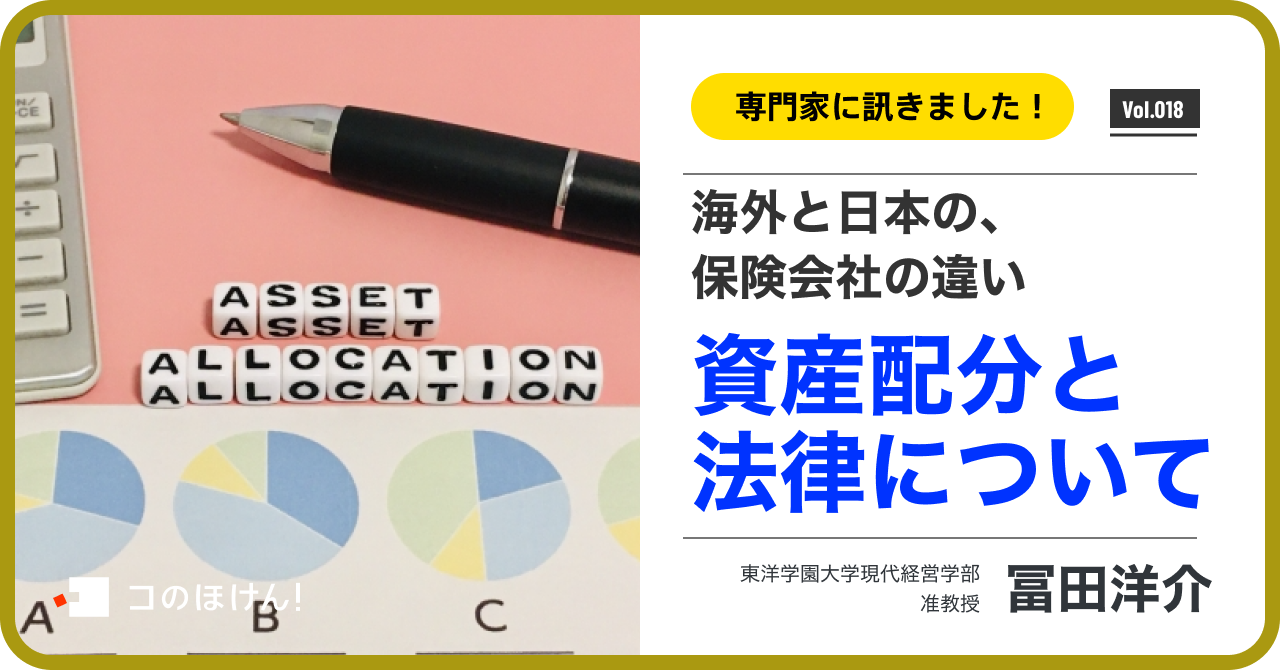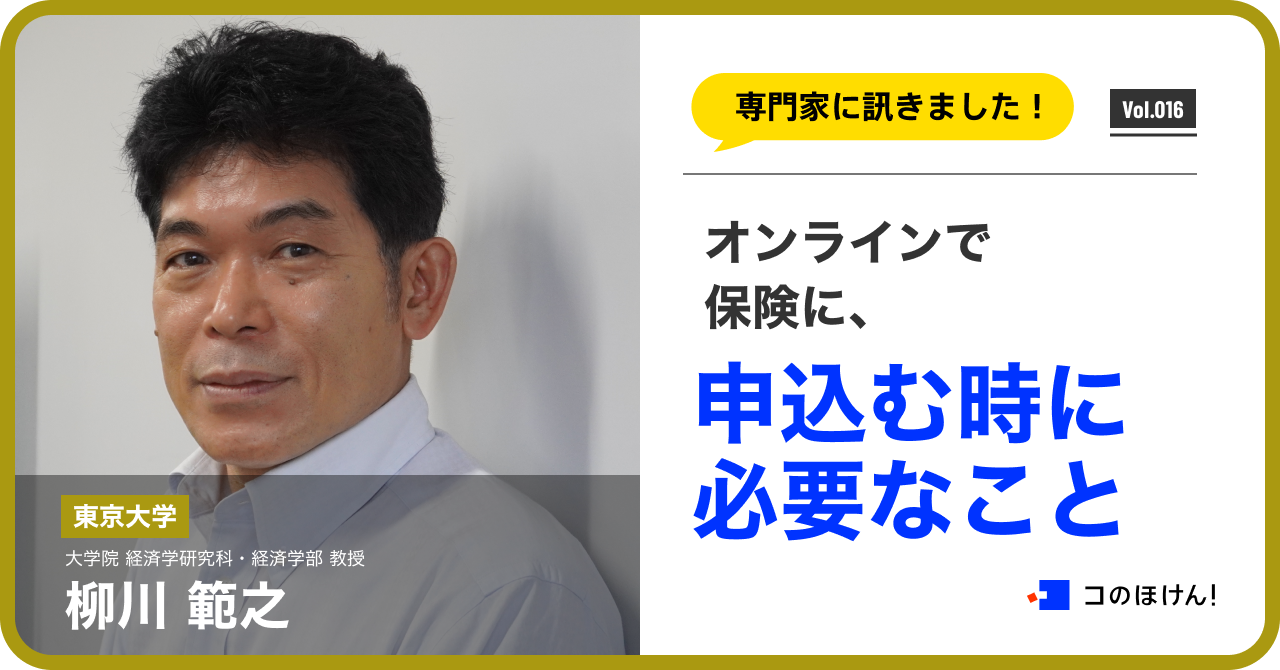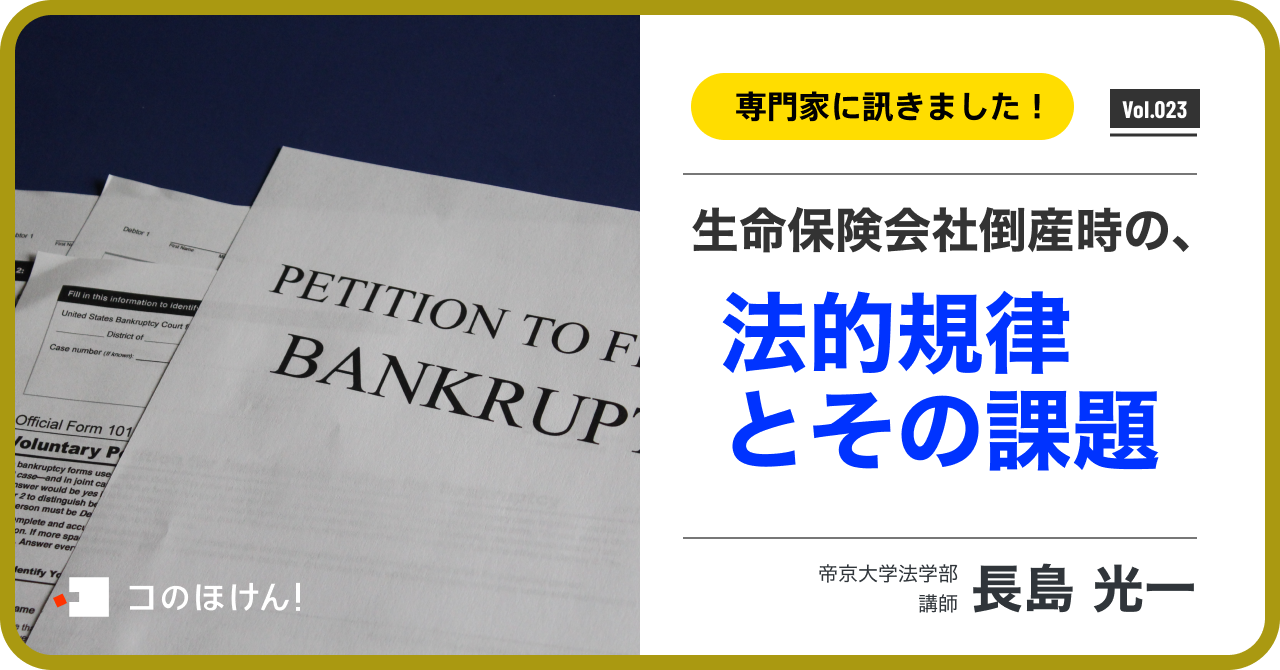
保険会社倒産時の生命保険をめぐる法的規律とその課題について
研究のきっかけ
コのほけん!編集部

長島先生
私は民事手続法という分野の研究をしており、これは民事裁判や紛争解決の手続きをテーマにした学問分野です。裁判といえば犯罪や刑事事件を思い浮かべがちですが、社会において実際には民事に関するものが多いです。保険や取引などの分野の紛争も、最終的には民事裁判で解決することになります。この民事の手続きには汎用性があり、いろいろな分野にも適用されます。
保険法に関するテーマを研究するきっかけは、(純粋ではないのですが)生命保険文化センターというところでアルバイトしたことです。そこでは、いろんな保険の判例を整理する仕事をしていました。その中で、保険金殺人のような社会的に注目される事件だけでなく、交通事故、入院など身近な問題も裁判になることがあり、民事手続きの研究をしている自分にとって、保険についても、民事裁判や民事手続きに様々な課題があることに気がつきました。
ここで、研究テーマに入る前に、保険法について説明します。保険法は商法の特別法であり、商法学者による保険法の研究が一般的です。しかし、保険には情報や消費者、税金、社会保障など多くの関連があります。保険は商法だけの問題ではなく、多くの分野と関連していることがわかります。
私が注目したのは、情報の問題です。裁判は情報戦の一種ともいえ、当事者は、裁判の中で情報を出し合ったり、逆に情報を隠したりすることもあり問題になります。そして、裁判所は、真実を発見するために情報をどのように取得するのかという問題もあります。この情報戦の中で特に注目すべき問題が、倒産をめぐる問題です。バブル崩壊やリーマンショックなどで金融機関が破綻し、この倒産によって多くの人々に影響を与えました。
金融機関の倒産は、一企業の倒産を超えて多くの人々に影響を与えるという事情がある中で、保険会社の持つ情報は、個人情報を含み、センシティブなものとして特別な側面から考える必要があります。自分の保険金はどう扱われるのか、また保険についての個人情報はどう扱われるのか、それが法律上の問題になります。こうした倒産をめぐる情報の取り扱いの問題は重要であると考え研究し、論文を書きました。
保険契約者保護機構とは?
コのほけん!編集部

長島先生
保険契約者保護機構による保護があることはそのとおりですが、実はその裏に隠された問題もあります。
そもそも、保険契約者保護機構はバブル崩壊やリーマンショックなどの金融危機の反省から創設され、保険会社が破綻した場合に保護されるしくみです。しかし、保護機構は原資があってのものであり、生命保険契約者保護機構の加入会社の負担金が前提となっています。財務状況が不安な場合には政府から資金援助が行われることがありますが、それは時限法となっており、期間制限がありました。具体的には2022年3月まででした。もっとも、5年延長され2027年3月までになっています。
コのほけん!編集部
知りませんでした。ニュースでは話題になっていませんね。
 長島先生
長島先生
そうですね。私が書いた論文は2019年で、当時調査する中で、政府が保険会社を支援するのに期間制限があると知り、これはどうなるのかと驚きました。現在はその期間が延長され一安心ですが、今後の状況を考えると、保険会社が倒産しても大丈夫なように政府の支援が引き続き必要といえるでしょう。今後の法改正がどのようなものになるのかは不透明であるため、この情報を引き続き注視する必要があるでしょう。
そもそも破綻とは一体何なのでしょうか?
一般的には「破綻」と言われますが、実際の法的処理としては、「破産」だけではなく、「民事再生」や「会社更生」など、破綻にも様々なバリエーションがあります。これらをまとめた概念として「倒産」といいます。
保険契約者保護機構は、破綻した保険会社が払うべき金銭を契約者に支払うことで手続きは終了しますが、民事再生や会社更生の場合には、会社が存続することを前提に様々な対応がなされます。保険会社の場合には、(適用されるケースがほとんどないのですが)会社更生法が適用されることが考えられ、法適用により会社が存続した場合に、これによって、新たな問題が起こることもあります。
会社更生の方法をとる場合、会社が存続することを前提にして、経営を安定化するための計画を立てることが重要になります。そうなると、保険契約者がそれに納得できるかどうかも問題になります。
一般の会社が破綻した場合、再生計画を作るために債権者と1対1で話をすることもありますが、保険会社の場合、債権者は保険契約をしていた人たちです。債権者全員と話すことは困難です。だからこそ、それらの人たちを一括で処理するために、保険契約者保護機構が設置されています。この保護機構により、政府からの資金援助を受けながら、保険契約者に対して金銭を支払うことで一括の破綻処理ができるわけです。
コのほけん!編集部
過去に確かに、日産生命が97年に倒産してプルデンシャルが引き継ぎをしたという、2000年代前後にかけて保険会社倒産がありましたけど訴訟もありましたね。倒産によって、実際にどのような影響があるのでしょうか。
 長島先生
長島先生
例えば、予定利率を下げたりするなど、債権者の権利を抑制することもあります。ただ、基本的にはその予定率は90%ぐらいを想定されているので、そこまで大きな影響はないとされています。しかし、それでも債権者の権利はある程度減少するため、納得いかない部分もあるかもしれません。
保険は様々な目的で加入されます。貯蓄やリスクの予防など様々です。保険会社の破綻後の処理によっては、期待していた保険加入の目的とは異なる状況になり、不満を感じることもあります。特に、会社更生の場合、管財人によって保険契約を存続させるかどうかを決められる権限があるため、保険契約の自由な解除が起こりうるという問題がありました。そうなると、他の保険会社との契約にも影響を与える可能性があります。また、高齢者や病気の方などは他に契約できないこともあり、解約されてしまった後の問題が発生する可能性が出てきます。
コのほけん!編集部
そういう風にならないようにするための仕組みはありますか?
 長島先生
長島先生
法律上はその問題を考慮して、管財人が自由に保険契約の解除をする選択をできないようになっています。保険というものは、様々なところに影響が出ますし、社会的にも影響が出るので、関連する法律の改正は頻繁に行われていて、特に破綻の問題については、定期的な議論と見直しがなされています。
保険会社倒産時における個人情報等の取り扱いについて
コのほけん!編集部
 長島先生
長島先生
個人情報は財産としても重要な価値があります。近年は、個人情報保護の法規制が進んでいますが、一方で情報の利活用も活発になっています。たとえば、性別や生年月日は、入学式や卒業式、結婚をはじめとするライフイベントの情報と直結する場合、それらの情報は個人情報として高い価値を持ちます。そのため、近年、個人情報保護に関する対策は積極的に取られています。
保険会社の場合には、保険契約者の個人情報や健康情報などを保険会社が保有していることから、それが流出する可能性があり、倒産後も同様です。情報の流出は、プライバシーに関する問題が発生します。そのため、保険会社は倒産した場合にも、個人情報の保護に関する法律や規制を遵守することが求められます。また、個人情報が流出した場合には、保険契約者に対して、適切な対応を行うことが求められます。
個人情報保護法は、個人の情報を保護するための法律ですが、一定のルールを守ることで個人情報の利活用を可能とする法律でもあります。保険会社もこの法律に準拠しなければならず、個人情報を適切に取り扱う必要があります。特に、破綻や倒産時においては、第三者への情報提供を避け、適切な処理が必要になります。
ところで、最近では、保険会社もビッグデータを活用して、InsurTechを導入していることもあります。そうしたビックデータも倒産時にどういう扱いになるのかという問題が考えられます。
実際、保険会社が破綻した場合には、会社をたたむ破産だけでなく、別の保険会社が吸収合併などをするようなケースもあります。そうなると、新しい保険会社にその元の保険会社の個人情報が移ることになります。その引き継ぎをする中で、個人情報の取り扱いが問題になります。
過去に、保険会社の不良債権処理のときに問題になったことがありますが、「バルクセール」という問題が起きます。これは不良債権の一括売却という問題です。要するに、その企業の持っているノウハウなども含めて全て一括で売ってしまうのですが、その中に個人情報が紛れ込んでいた場合、それがどう使われるのかがわからないという問題が起こります。
吸収合併する企業がどういう企業なのかという点は結構大事な問題で、安心できるきちんとした企業だったら個人情報もきちんと扱ってくれると思うのですが、場合によってはずさんな管理により不適切な利用などの問題が起こりうるのです。
コのほけん!編集部
実際の事例はありますか?
 長島先生
長島先生
個人情報の流出事例は度々報道されていますが、それによる実際の不適切利用ケースはあまり意識されてこなかった部分ですので、表に出てきた事例はほとんどないと思います。ただ、水面下で個人情報の不適切な取り扱いを受けたケースはこれまでもあり得たのではないかと思われます。
保険に関する情報は個人情報の中でも要保護性の高い情報といえますが、現在の個人情報保護法では、個人情報の利用目的が同じである吸収合併した企業であれば、その情報を利用できるとされていますが、利用目的が異なる場合は、本人からの新たな同意が必要となります。病歴などを含む保険の情報は、「要配慮個人情報」に該当するものもあると思われますで、改めて本人同意をしない限りは使えない場合もあるでしょう。
個人情報保護の問題への対応としては、個人情報保護法による規律だけでなく、個人情報保護委員会がガイドラインを出しています。金融庁によるガイドラインや安全管理措置の指針なども作られています。これらは、具体的かつ保険会社に厳しい内容で、個人情報の流用ができないように考えられています。これらを遵守する限りは、安心安全な配慮がされるはずです。
ただ、一方で、こうしたガイドラインに反して利用されてしまった事例もあるため、この辺りはきちんと業界内対応で監視体制を作るなど、対応を具体化する取り組みが必要と思われます。
一般企業が倒産した時に保険金をめぐってトラブルになる事例はあるのか?
コのほけん!編集部
 長島先生
長島先生
保険契約者と保険金の受取人が同じである場合には、問題はあまり起きませんが、契約者と受取人が異なる場合に問題が起こることがあります。
一般に、受取人は、被保険者(契約者)に万が一のことがあった場合に保険金が支払われるということを前提に、受取人が個人であれば生活保障として、企業であれば事業承継や存続のための資金として、将来設計をしている可能性があります。
しかし、一般企業も含めた契約者が倒産しまった場合には、その契約者側の債権者がその保険金をよこせという問題が出てきます。つまり、保険契約を解除して解約返戻金を財源にして債権者で分配したいという問題が出てくるわけです。
この問題については一応法改正による対応がなされています。「介入権」といいますが、 契約者が倒産したとしても、受取人の保護という観点から、契約者の親族でかつ受取人本人とその家族であった者など、対象は限定されていますが、解約返戻金相当額を払う代わりに保険契約を守ることが可能です。これによって、保険契約者と受取人が異なることによる問題については、一応は解決しているとされます。
しかし、対象が限られていますし、そもそも、受取人自身、自分が受取人であることを知らない場合もあります。また、保険契約者が倒産しても、代理人や管財人が保険契約の存在を知らないままのケースもあります。これらは、本当は受け取る権利あったにも関わらず、何もせずに倒産処理手続きが終わってしまう事例であり、処理後に発覚した場合に、その手続を蒸し返すことにもなります。
こうしたことが起こってしまう背景には、コミュニケーションの問題があります。保険会社は受取人が誰なのかという情報を持っていますが、受取人を含めた当事者たちは実は知らないというケースがあります。こうした実態から考えると、 保険会社と保険契約者、保険契約者と保険金受取人などのコミュニケーション不足が事後的なトラブルに繋がっているといえます。
日頃から保険の情報を関係者の間でどのように共有するのかという課題があるでしょう。
倒産時の生命保険をめぐる法規制の現在の課題、また今後の動向
コのほけん!編集部
 長島先生
長島先生
これまでお話ししたように、保険会社が倒産した場合だけでなく、契約者や受取人が倒産した場合にも、様々な保険に関する問題が発生しています。こうした問題に対し、法改正などで対応してきた部分も多くあります。保険会社の破綻処理では契約者保護の観点から議論されて対応がされてきました。
しかし、保険の問題はそこで終わるものではありません。コロナ禍の中で、一般企業の倒産も増加し、新たな保険の問題がこれから出てくるかもしれません。今後、新しいリスクがいつどこで起こるのかもわからないため、新しい問題に対応できるような保険の仕組みを検討することも必要でしょう。
もちろん、現行の法律で対応できれば最善ですが、保険の場合はそうもいきません。集団処理の問題が発生するため、いざというときのために、包括的な制度改正を視野に入れた検討する必要があります。 人々が知らないところで、保険に関わる重要な議論がされていたりもするので、アンテナを張って情報収集をしたほうがよいでしょう。自分の身を守るためにも重要です。
コのほけん!編集部
インターネットで情報収集がある程度はできると思いますが、どういったところのサイトを見たらいいというのはありますか。
 長島先生
長島先生
倒産分野で必要な情報がまとまっている情報収集源はあまりありませんが、保険分野では金融庁、個人情報では総務省などが重要な情報(法改正状況やガイドライン)を出していますので、そこを確認するという方法がよいでしょう。
まとめ(編集部後記)
今回のインタビューでは、保険契約者や受取人が倒産した際に起こりうる問題について、長島先生から詳しい説明をうかがうことができました。保険会社や法規制の改善は進んでいるものの、今後も新たな問題が起こる可能性があるため、情報収集が重要だといえます。また、金融庁や総務省などが重要な情報を提供しているため、こうした公的な情報を把握することが大切だと感じました。
.jpg)