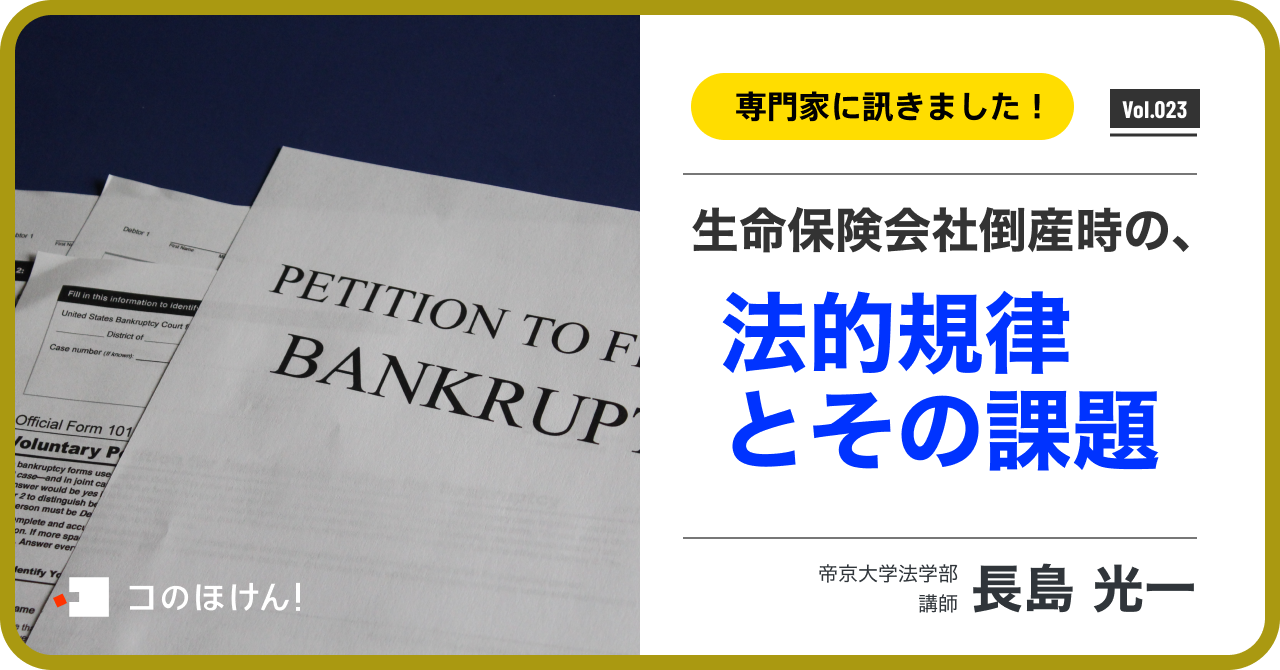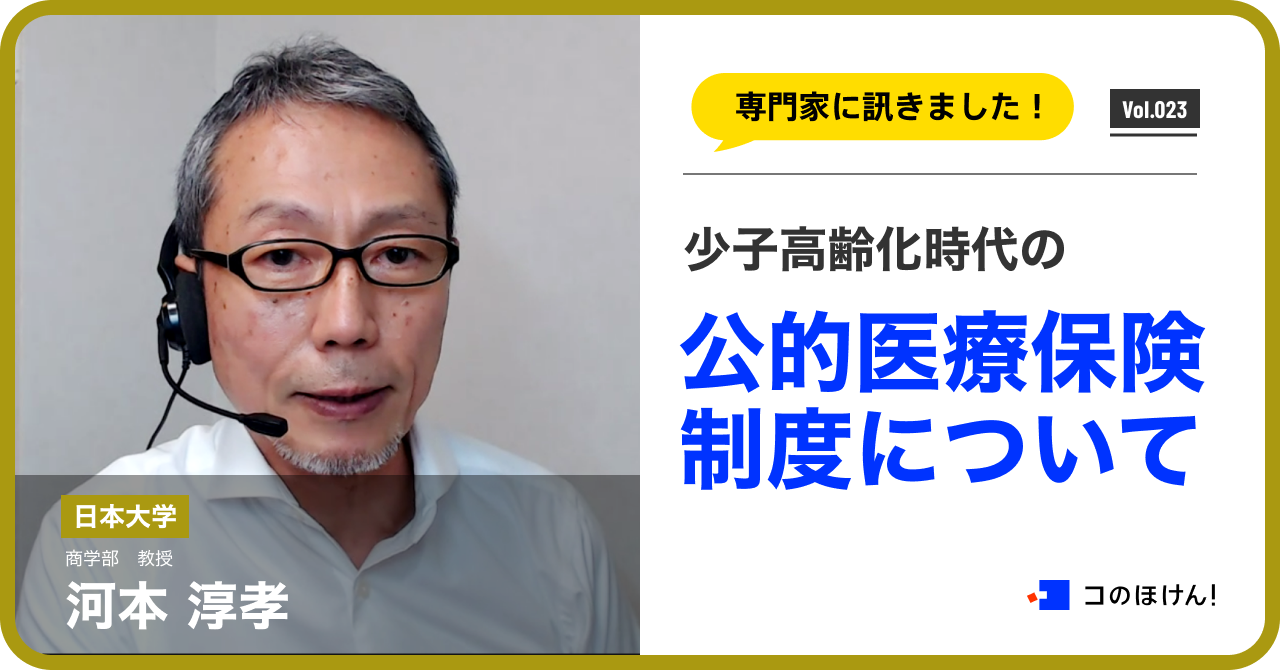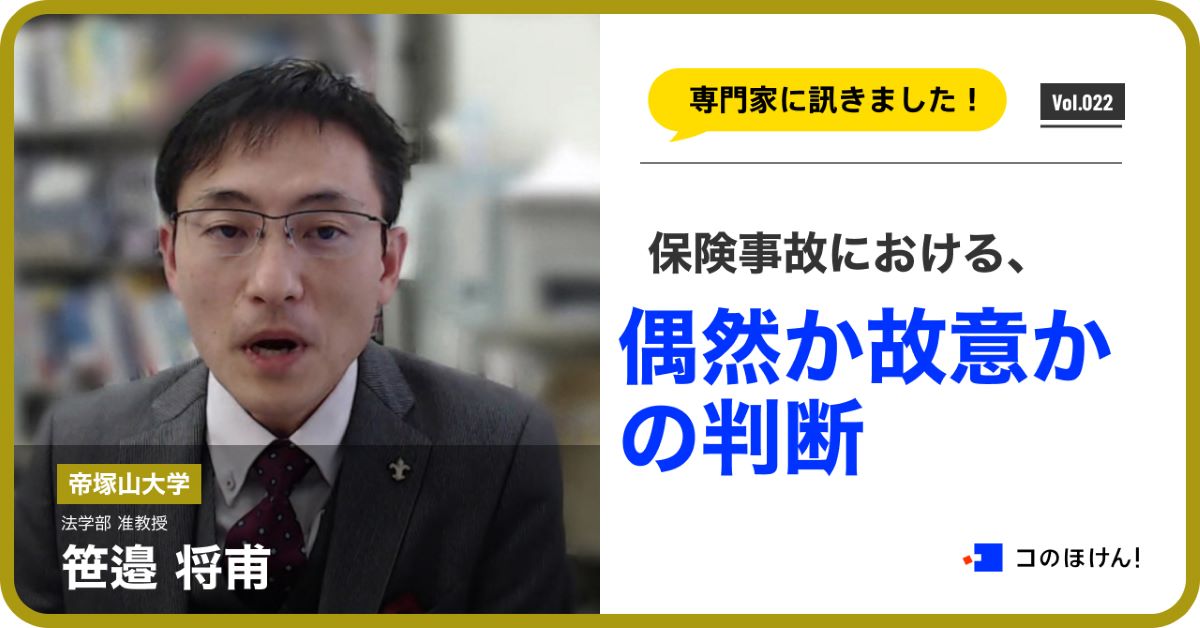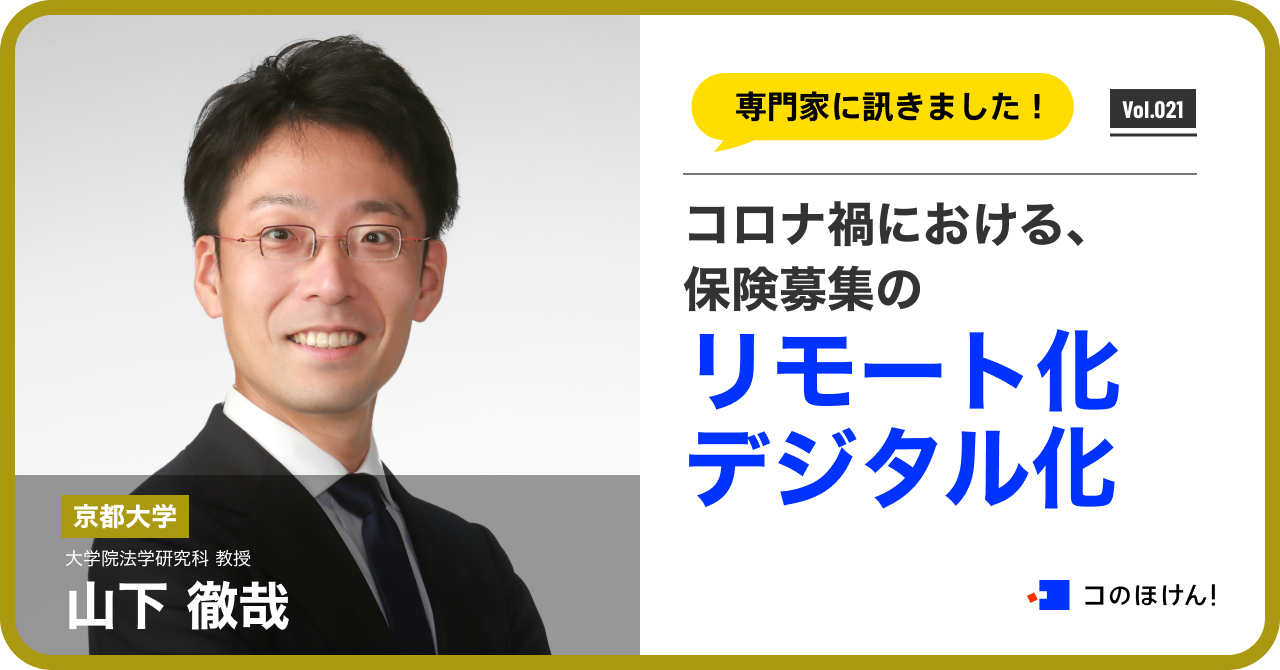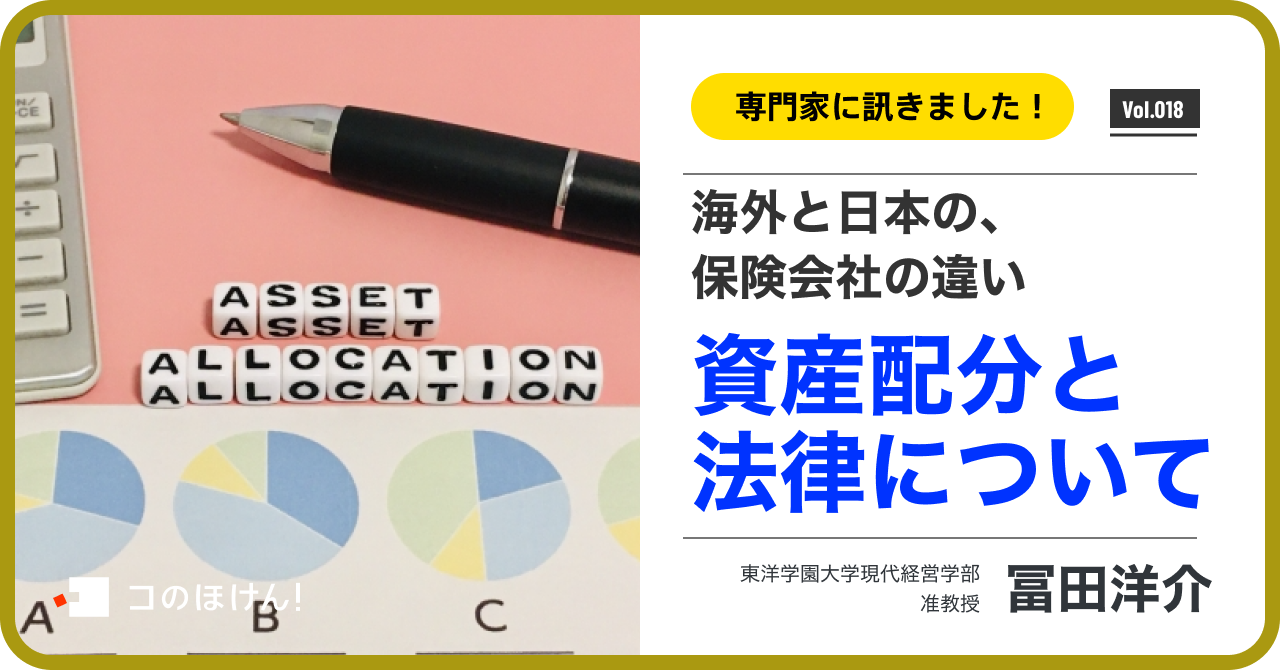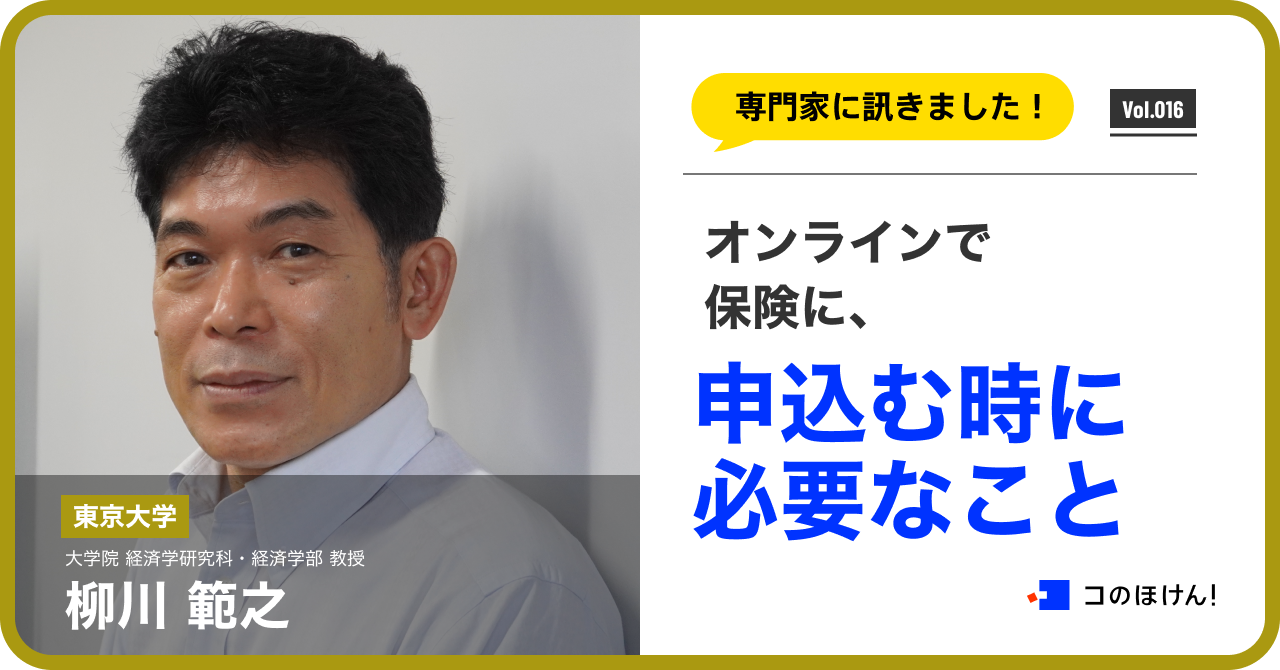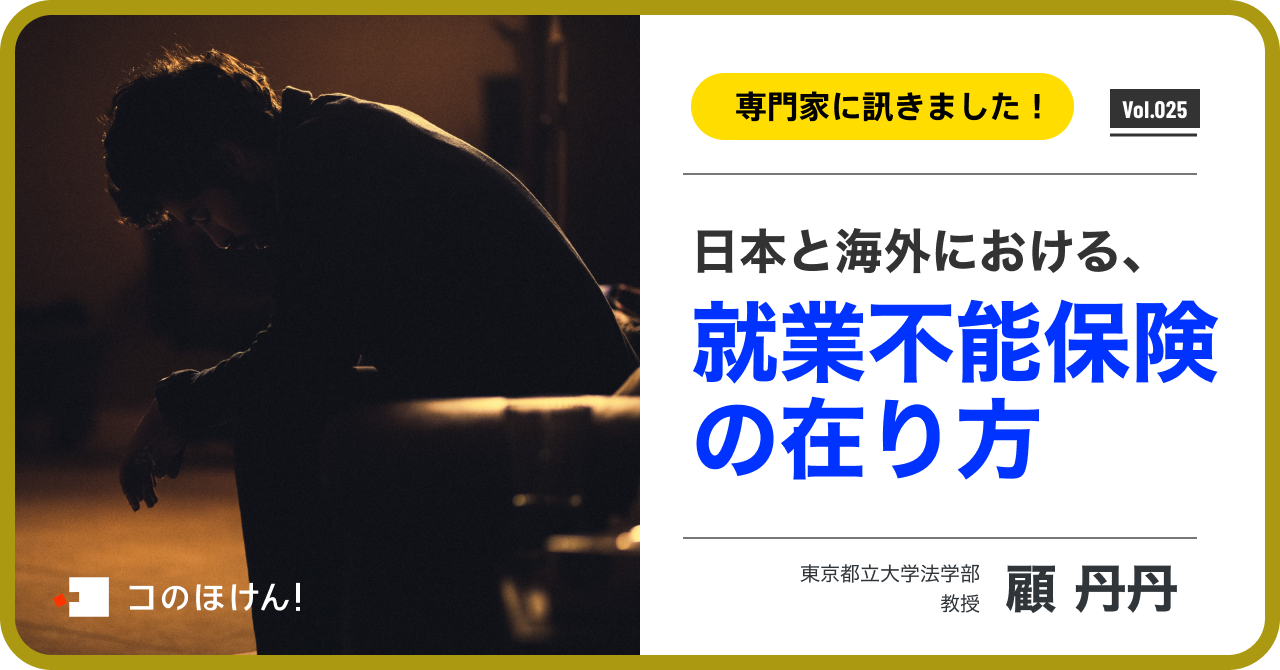
就業不能保険の在り方について
研究のきっかけ
コのほけん!編集部

関心を持ったきっかけは学生時代に勉強した平成元年1月19日の最高裁判例でした。
就業不能保険(欧米ではディサビリティ保険)は、就業不能による所得の減少ないし喪失を補償する保険の総称であって、この種類の保険は概ね、損害保険会社が提供する「所得補償保険」と生命保険会社が提供する「就業不能保障保険」という2種類に大別されています。平成元年1月19日の最高裁判例では、前者の「所得補償保険」の法的性質(損害てん補性のある保険といえるか)が争われました。
日本の保険法においては保険契約の性質、つまり損害保険か定額保険かによって、適用される法規定が異なるため、非常に興味深い判例です。
就業不能保険の誕生の背景
コのほけん!編集部

就業不能保険には、損害保険会社が販売する「所得補償保険」と、生命保険会社が販売する「就業不能保障保険」との2種類があります。後者の「就業不能保障保険」は、1990年代、1992年に当時の明治生命、現在の明治安田生命が販売したのが最初です。ただ、実は1970年代、1974年に当時の安田火災海上保険、現在の損保ジャパンから「所得補償保険」がすでに販売されていました。
商品開発の理由は、欧米で販売されているこの種類の保険は日本市場にもニーズがあると判断したからだと推測しております。
実際は1974年に安田火災海上保険株式会社から「所得補償保険」が発売され、短期間に高い売上成長率があったようです。その後、1992年に明治生命から保険金の支払期間をより長くした「長期就業不能保険」が発売されました。
ただ、その後長い間、一般的な認知度は高くなかったようで、日本の就業不能保険は市場規模がそれほど大きくありません。
近年、同じく就業不能保険のカテゴリーに入る、様々な名称の保険商品は保険各社から販売されるようになっています。その背景には、一方で、単身世帯や女性の社会進出の増加に伴って、就業不能となった場合に、収入が減少または喪失し、生活費の確保や生活水準の維持に不安を感じる人が増加しているという事実があるかと思われます。他方で、就業不能保険が属する第三分野の保険市場では、生命保険、損害保険各社の競争が増しているという業界の実情もあろうかと思われます。
損害保険の所得補償保険やGLTDとの違いは?
コのほけん!編集部

GLTDつまり「団体長期保障所得補償保険」は、損害保険会社が団体保険として提供する長期保障の就業不能保険です。生命保険会社も団体保険を提供していますが、「長期就業不能保障保険」という名称を用いているようです。
団体保険と個人向けの保険との違いは、主に法律関係と契約の手続きにあります。団体保険の場合は、被保険者の勤めている会社や所属している専門職業団体が保険契約者となり、保険会社と保険契約を締結します。個人向けの保険の場合は、被保険者は自分自身が保険契約者として、保険会社との間で保険契約を締結します。また、団体保険は加入時の審査や手続きが個人向けの保険と異なります。
約款つまり保険契約の内容については、団体保険の場合は約款が一般公開されていなかったので、契約内容の詳細を確認することができなかったが、保険契約の内容それ自体には大きな違いがないと思われます。
保険契約の内容に大きな違いがあるのは、むしろ「所得補償保険」と「就業不能保障保険」です。保険契約の内容が異なると、保険契約者が支払う保険料も異なります。
全体として、損害保険会社が提供する「所得補償保険」は、保険金の支払期間が1〜2年程度、短期補償しか提供しないものが主流です。他方で、生命保険会社が提供する「就業不能保障保険」は、保険金の支払期間が、就業不能状態がなくなった時または保険期間の満了時まで、保険期間が通常、55歳・60歳・65歳・70歳まで等の5歳刻みで長く設定していますので、長期保障を提供する商品設計となっています。
次に、保険金の支払事由・給付事由、要するに保険金を支払ってもらうために満たすべき要件も異なります。「就業不能保障保険」では、「就業不能」の定義がより限定的で、多くの場合は、国民年金法に基づく障害等級2級以上またはそれに相当する重大な障害状態等に限定しているため、重大な身体障害がない場合には保険金の支払事由を満たすことができないものになっています。「所得補償保険」では、「就業不能」の定義がより広く、被保険者がけがまたは病気により治療のために入院していること、治療を受けていること、あるいは約款所定の後遺障害によって、保険証券記載の業務に従事できない状態等であれば、保険金が支払われます。
さらに、契約の継続・更新の方法にも違いがあります。「就業不能保障保険」は通常、保険期間が変更できず、契約締結時と同額の保険料が支払われる限り、契約は原則として期間満了まで自動更新され継続されます。他方、「所得補償保険」は、保険期間満了日に契約が自動的に継続・更新するものではなく、保険事故が起きた場合の支払い内容等により、契約の継続・更新が不可となったり、継続契約の条件が制限されたりすることもあるようです。
就業不能保険のメリット・デメリット
コのほけん!編集部

保険は、基本的に人によって必要の程度が異なります。消費者の立場からすると、どの程度リスクを回避したいか、特に、保険事故にあたる状況が起きた場合にその影響をどの程度抑えたいかによって、保険に対するニーズが変わってくると思います。
就業不能保険は勤労世帯に向けた保険商品であって、働いている間に、けがや病気によって休業せざるを得ない場合に、所得が減少または喪失するリスクに備えるための保険商品ですので、対象になっているのは実際に働いている方です。また、対応しているリスクは公的保険、正確には公的所得保障制度でもある程度カバーされているので、適用を受ける公的所得保障制度にもよります。
日本では、代表的な公的所得保障制度として、国民年金法・厚生年金法に基づく障害基礎年金・障害厚生年金、健康保険法・各種共済組合法等に基づく傷病手当金および労働災害補償保険法に基づく労災休業補償等があります。けがや病気の結果、大きな、かつ持続的な身体障害があった場合には、国民年金法や厚生年金法によって定められている障害年金が支給されます。一時的な休業の場合には、健康保険法等に基づく傷病手当金等が支払われることがあります。
後者の傷病手当金については、職種により、法的に加入を求めている健康保険の種類が異なりますので、ある場合とない場合があります。例えば、会社勤めの方は通常、健康保険法が適用され、休業となった場合には最大1年6ヶ月の傷病手当金を受け取ることができます。また、公務員等共済組合法の適用を受ける方でも、同様に傷病手当金を受け取ることができます。ただ、自営業者やフリーランスのような個人事業主は、国民健康保険に加入するのですが、傷病手当金の支給はありません。
傷病手当金の支給がある場合でも、1年6ヶ月を超えた就業不能のリスクに備えたいのであれば、民間保険の「所得補償保険」または「就業不能保障保険」を検討することになると思います。
自営業者やフリーランスのような個人事業主は、国民健康保険からは傷病手当金の支給がないため、一時的な休業のリスクに備えるために、就業不能保険を検討するのが合理的な判断といえるかもしれません。
研究者として裁判例を調べて受けた印象としては、当事者が医師等の事案が多く、特に病院やクリニックを経営している開業医で、所得水準も比較的高い方は就業不能保険に加入することが多いようにみられます。
就業不能保険における課題と展望
コのほけん!編集部

最も大きな課題は、保険金の支払事由・給付事由にあたる「就業不能」の判断と、就業不能となった被保険者に対する職場復帰のインセンティブの与え方にあるのではないかと思われます。
特に「就業不能保障保険」のような長期保障を提供する保険では、就業不能状態が継続している限り、保険金が支払われるという仕組みになっています。しかし、保険者(保険会社)にとっては、客観的にみて、被保険者が就業不能状態にあるか、いったん就業不能となった被保険者が職場へ復帰できないかを判断することが必ずしも容易ではありません。
被保険者は長期間にわたって保険金を受け取りたいと考えるのも当然かもしれませんが、保険金の支払事由・給付事由を満たしていない者に対して保険金を支払うことは、他の保険加入者に負担をかけることになります。安易にこれを認めると、長期的には保険のシステムそれ自体が維持できなくなる可能性があります。他方、保険者(保険会社)は、支払事由・給付事由の判断を正確に行おうとすれば、訴訟へ持ち込む場合の訴訟費用を含めて、過大な運営コストが発生してしまう懸念があります。
もう一つの課題は、就業不能となった被保険者に職場へ復帰するインセンティブの与え方です。この点についてはアメリカの就業不能保険から参考できる点があると思います。
アメリカでは就業不能保険が広く販売されており、市場の規模も大きいですが、日本と比較すると、職場復帰のインセンティブを高めるための工夫がされているという特徴がみられます。
例えば、日本の就業不能保険は、完全に働けなくなった場合に所得の喪失を補償する保険となっていますが、アメリカでは部分的就業不能特約が付帯される保険も販売されています。これは、完全に働けないのではなく、例えば週に数日は働ける、または常勤から非常勤に変更する場合でも、一定額の保険金が支払われるという特約です。このような特約を活用することで、被保険者の職場復帰に向けたインセンティブを高めることができます。
また、アメリカの就業不能保険では、完全に復帰するまでの間に、保険金以外の形で経済支援を提供することもあります。例えば、被保険者が実際に職場に復帰した場合でも、就業不能の状態がなくなったので、保険会社は保険金を支払わないが、一定期間、復帰するための経済支援を行うといった復帰支援特約も利用されているようです。
日本では、このような復帰支援特約は、一部の保険会社が販売する就業不能保険に付帯されていますが、普及しているとは言えません。もう少し積極的に導入する余地があると考えられます。
まとめ(編集部後記)
顧教授のインタビューを通じて、就業不能保険の成り立ちやアメリカとの日本の違いが明らかになりました。特に、アメリカでは部分的就業不能保険や復帰支援特約が広く活用されており、日本ではまだ一般的ではないことがわかりました。そのような保障があることで、復帰できる人はもっと復帰を目指す努力をすることができる可能性があると考えられます。今後は、働けない間だけの保障だけでなく、職場復帰を支援するような形で保障を拡充する可能性もあるのかもしれません。




.jpg)