2026年1月版68歳女性がん保険おすすめ人気ランキング
多い順番にランキング形式でご紹介します。
ランキング
比較表がん保険の
申込者データ
申込者の性別

申込者の年代

月払平均保険料

| 年代 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 20代以下 | 1,269円 | 2,386円 |
| 30代 | 3,452円 | 3,077円 |
| 40代 | 4,323円 | 3,676円 |
| 50代 | 4,775円 | 3,272円 |
| 60代 | 4,939円 | 3,831円 |
| 70代以上 | 5,279円 | 3,459円 |
- ※ 2023年8月1日~2024年9月30日の間にコのほけん!経由でお申込みいただいたデータを集計
- ※ お申込み方法が対面で保険の払込方法が「月払」の方のみ対象
- ※ 保険会社ごとに保障内容・保障額が異なり記載の数値は参考となりますので、お申込みにあたっては必要な保障を十分にご検討いただきますようお願いします。
60代が知っておくべきがん保険の基礎知識
更新日:2025年7月9日
60代は、子どもの独立や定年退職など大きなライフイベントを経験し、シニア世代として老後の生活が始まる人が多くなります。 しかし一方で、60代はセカンドライフへの期待とともに、健康について不安や悩みを抱えることが多くなる年代ともいえます。がんのリスクも決して例外ではなく、60代は他の年代に比べがんのリスクが特に高い年代です。 がん保険ではがんに備えることができるため、安心感につながりますが、どのようなポイントでがん保険を選べばよいか悩む方も多いでしょう。 この記事では、60代に必要ながん保険の基礎知識や選び方、また加入時の注意点など押さえておきたいポイントについて解説します。
シニア世代のがんリスクとがん保険の重要性
シニア世代になるとがんの発症率が上がりますが、定年退職で定期的な収入がなくなる人も多い60代にとっては、万が一がんになった際には治療費が経済的負担となることが考えられます。
がん保険は治療費をサポートし、経済的安心を提供します。ここでは、60代におけるがん保険の重要性を、がんのデータなどから解説します。
60代ががんになるリスクはどれくらい?
60代は、他の年代に比べがんのリスクが高い年代です。
国立がん研究センターの調査によると、2021年の各年代ごとのがん罹患率(1年間に人口10万人あたり新規にがんと診断された例)は、以下の通りでした。

※出典:国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(全国がん登録)より表を作成
一般的に、がんは30代後半以降から罹患率が高まる病気ですが、年代を通して見てみると50代から60代に入り大幅に増加していることがわかります。
では、60代の男性・女性に多いがんには、どのような特徴があるのでしょうか。
以下は、国立がん研究センターの調査に基づく、60代の男性・女性で罹患率の多いがん(部位別)のランキングです。
| 60-64歳 | 65-69歳 | ||
|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | |
1位 | 大腸 | 乳房 | 前立腺 | 乳房 |
2位 | 前立腺 | 大腸 | 大腸 | 大腸 |
3位 | 肺 | 肺 | 肺 | 結腸 |
※出典:国立がん研究センターがん情報サービス「がん統計」(全国がん登録)より表を作成
60代の前半では、男性は50代から多くなる大腸がんが最も多く、次に男性特有のがんである前立腺がんがランクインしています。また、女性で最も多いのは女性特有のがんである乳房のがんとなりますが、男女ともに3位には肺のがんが入っています。
一方で、60代後半では、男性は前立腺がんが最も多いがんとなり、女性は乳房のがんが依然として最も多いものの、結腸のがんなど、また異なる種類のがんがランクインしています。
なお、肺がんは、長年の喫煙や受動喫煙の影響で発症する可能性が高くなるがんです。60代は男性・女性特有のがんだけではなく、今までの生活習慣を原因としたがんにも気を付けなければならないことがわかります。
60代にがん保険が必要な理由
60代でがん保険が必要とされる理由は、経済的負担の軽減と安心感の確保にあります。がん保険は、万が一の発症時に治療費や生活費をカバーする手段として有効であり、心の備えとしても安心感をもたらします。
がんは、定期的な健康診断やがん検診を受けることで、早期に発見し治療を始めることができます。しかし、60代は定年退職により、会社などが実施する定期的な健康診断を受ける機会が減少する人もいるため、がんの発見が遅れる可能性もあります。
60代は健康管理を見直し、がんの予防や早期発見に努めることが一層重要な年代ですが、万が一の事態も想定し、がん保険で備えておく必要性も高いといえます。保障が適切ながん保険を選び加入しておくことで、万が一の際にも経済的な負担を軽減し、安心して治療に専念することができます。
また、がん治療には高額な医療費がかかることが多いため、会社を退職し収入が減少する60代にとって、がん治療にかかる費用が家計へ大きな影響を及ぼすことも考えられます。
こうした経済的リスクに対し、がん保険であらかじめ備えておくことで、セカンドライフも安心して楽しめ、生活の質を向上させる助けとなります。
60代におすすめのがん保険の選び方
がん保険を選ぶ際には、保障内容と保険料のバランスを慎重に検討し、自分のライフスタイルに合ったプランを選ぶことが大切です。特に、特約で追加できる保障や、それぞれの給付金の支払い条件についても確認しておくと、より安心です。
ここでは、60代でがん保険を選ぶ際の重要なポイントについて解説します。がん保険の加入前に確認しておきたい保障のポイントや、定期型と終身型といったがん保険のタイプ、健康に不安がある場合の選択肢について説明します。
加入時に確認すべきポイント
60代でがん保険に加入する際は、まず契約内容を理解することが重要です。
診断給付金や入院給付金などの基本的な保障内容が充実しているか確認するとともに、保険料の支払い方法や保障の期間も必ず検討しましょう。
また、がん保険は契約に特約を付加することで、補償内容を手厚くしたり、新たな保障を加えたりすることができます。
昨今メインとなっている、通院メインのがん治療も想定し、通院保障を手厚くする特約や、公的医療保険制度でカバーできない先進医療や自由診療に対する特約などを中心に、確認してみるのがおすすめです。
また、がん保険の保険料が、長期的に支払い続けられる金額かチェックすることも確認しましょう。家計や老後の生活資金のバランスも踏まえたうえで、無理のない範囲で支払いが可能か検討することをおすすめします。
さらに、がん保険を検討する際には、必ず複数社の商品を比較・検討しましょう。がん保険の比較サイトでは、商品の比較だけではなく、保険会社のサポート体制や給付金の支払いなどについて、契約者からの口コミが投稿されていることもあります。様々な観点からがん保険を検討することができますので、ぜひ積極的に利用してみましょう。
もし、自分に合ったがん保険がわからない際には、ファイナンシャルプランナーなどがん保険をよく知る保険のプロに相談してみるのもおすすめです。
定期型と終身型について
がん保険には、定期型と終身型というふたつのタイプがあります。
定期型のがん保険は、保障は一定期間のみとなりますが、保険料が比較的安価であることが大きな特徴です。しかし一方で、定期型は契約更新時の年齢や健康状態によって、保険料が大きく上がる可能性があることに注意が必要です。
一方で、終身型のがん保険は一生涯保障が続き、保険料が契約時のまま変わらないのが一般的です。契約更新の必要もないため、長期的な安心感がありますが、保険料は定期型よりも高く設定されている傾向があります。
定期型のがん保険は、ある一定期間のがんに対する保障を求める場合に適していますが、更新ごとに保険料が高額になった場合には、長期的に見ると保険料が割高である可能性があります。
終身型のがん保険は、保障が一生涯であり安心感が大きい一方で、定期型に比べ保険料は高いため、のちのち収入が減少したりした際には、保険料の支払いが大きな負担になる可能性があります。
ただし、60代で新たにがん保険に加入する場合、健康状態や告知内容によっては定期型・終身型のどちらも保険料が高めに設定される可能性があるため、あらかじめ注意が必要です。
60代は将来の医療費や老後資金を見据えた計画が必要となるため、がん保険のタイプを選ぶ際には、現在の健康状態やライフスタイル、経済状況を考慮したうえで、自分に合ったものを選ぶことが重要です。
健康に不安がある場合の選択肢
一般的に、がん保険は年齢が上がると保険料も高くなります。よって、がん保険への加入が早ければ早いほど、保険料は安価に設定される一方で、健康状態や既往歴、持病の有無なども保険料に影響を及ぼします。
もし、60代で健康状態が思わしくなかったり、重い既往歴や持病があったりすれば、保険料が高く設定される可能性があるだけではなく、保険会社からがん保険への加入を断られる可能性があります。
しかし、もし通常のがん保険への加入を断られても、引受基準緩和型がん保険に入るという選択肢があります。
引受基準緩和型がん保険は、病気・持病がある方でも入りやすくなっているがん保険で、加入時の告知内容が通常のがん保険より緩やかに設定されています。よって、既往歴や持病があり、健康状態が思わしくない方でも入りやすいがん保険となっています。
ただし、引受基準緩和型がん保険は通常のがん保険に比べ保険料は高く、加入にあたっては保障が限定されたり、条件付となったりする可能性もあります。
よって、もし60代で健康に不安があり、通常のがん保険への加入が難しいと考えている方も、まずは通常のがん保険から検討してみましょう。引受基準緩和型のがん保険は、最後の選択肢として残しておくのがおすすめです。
60代でがん保険に加入する際の注意点
60代でがん保険に加入する際には、保険料の負担や保障内容をしっかり確認することが重要です。
ここでは、保険料の負担を軽減する方法、保障内容の選び方、既往歴がある場合の注意点について解説します。自身の健康状態やライフスタイルに合った保険を選び、安心して充実したセカンドライフを迎えましょう。
健康なうちに加入を検討する
60代は、急な病気やケガに見舞われるリスクが高くなります。もし健康状態が悪化すると、がん保険への加入が難しくなることもあるため、ぜひ健康なうちにがん保険を検討し、加入までしておくのがおすすめです。
また、定年退職前で、今後収入が減少する可能性が高い場合、保険料が長期的に支払い続けられる額か、必ず確認しましょう。
がん保険でカバーできる範囲を確認すると同時に、入院が長引くことも想定して、入院費用や手術費用が適切か確認しておくのも重要です。さらに、特約や給付金の額もしっかり確認しておきましょう。
給付金・保険金の受け取り条件を確認する
がん保険の給付金や保険金を受け取るための条件や、手続きについて確認しておくことも重要です。
一般的に、がん保険の給付金や保険金を受け取るには、いくつかの条件を満たすとともに、所定の手続きが必要となります。
例えば、がんの診断給付金を受け取る際には、医師の診断書が必要で、診断日から一定期間内に請求する必要があります。また、がんの診断給付金は、契約時に定められた待機期間中にがんと診断された場合は支払い対象外となるため、注意が必要です。他にも、がんの種類によっては給付金の支給対象外となることもあります。
また、給付金の請求手続きには保険会社所定の必要書類の提出が必要であり、給付金や保険金をスムーズに受け取るには、迅速な手続きが求められます。
契約時に渡される契約のしおりや約款を確認し、給付金・保険金の受け取り条件や、受け取るための手続きや連絡先を把握しておくようにしましょう。
もし、不安がある際には、配偶者や家族、また近しい人と一緒に保障内容や給付金・保険金の受け取り条件や手続きについて確認したり、共有したりしておくとよいでしょう。
がん保険に加入する際には、自分にもしものことがあった場合にも、代わりの人が給付金や保険金を受け取るための手続きができる体制を整えておくことも心掛けましょう。
まとめ
がんになるリスクが高い60代が、がん保険を選ぶ際には、保険料の負担と長期的な保障を確認し、定期型や終身型の特徴を理解してライフスタイルに合ったものを選ぶとよいでしょう。
60代でのがん保険選びは、これまでの健康状態や病歴を考慮し、適切な保障内容を選ぶことが重要です。また、がん保険は基本的な保障だけではなく、治療期間中の経済的な負担を軽減する特約も検討することをおすすめします。
加入前には、給付金の受け取り条件や契約内容を確認し、万が一の際にはスムーズに給付金や保険金の請求ができる体制を整えておくことも重要です。不安な場合は、家族など近しい人にも共有しておきましょう。
また、保険に加入したら定期的な見直しも忘れずに行い、今のがん治療の実態に即した保障内容にアップデートしておくことが重要です。
もし自分に合ったがん保険がわからなったり、ひとりで選ぶことに不安を感じたりする際には、ファイナンシャルプランナーなど保険のプロに相談するのもおすすめです。無料の相談サービスなどを、まずは気軽に一度利用してみるのもおすすめです。
がん保険を動画で解説
こちらの動画でもがん保険についてわかりやすく解説をしています。「がん保険は本当に必要か」「がん治療にかかるお金」についてさらに深く知りたい方は、ぜひ参考にしてください。
がんはいまや日本人の2人に1人が生涯に経験すると言われる身近な病気です。がんの専門家や当事者へのインタビューを通じ、がんと向き合うためのヒントを紹介します。
がん保険をテーマにした保険のコラムの一覧です。『がん保険とは?』『がん保険の必要性は?』などの話から基礎知識の解説など、保険選びに役立つトピックスを掲載しています。
がん保険ご相談者様の声
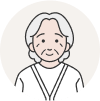
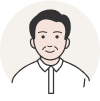
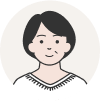
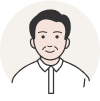
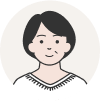



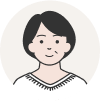
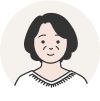
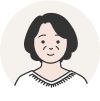
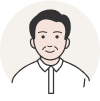
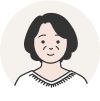
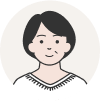
- 「ご相談者様の声」は、主観的なご意見・ご感想であり、価値を客観的に評価するものではありません。あくまでも一つの参考としてご活用ください。
- ご相談者様からいただいた声の中から当社で抽出・編集して掲載しています。
がん保険でよくある質問
 がんになったら医療費はいくらくらい必要になりますか?
がんになったら医療費はいくらくらい必要になりますか?
がん治療の費用相場は、がんになった部位やがんの進行度(症状)・治療の期間・方法によって様々で、低いものだと数十万円〜、高いケースでは数百万円まで幅があります。
 がん診断給付金とは何ですか?
がん診断給付金とは何ですか?
一般的ながん保険の基本保障には、入院日数や通院日数に応じて受け取れる「入院給付金」や「通院給付金」、がんの手術を対象とした「手術給付金」があります。加えてがん保険には、がんと診断が出た際にほかの給付金より早く手元に入る「がん診断一時金」があり、これががん保険の特徴とも言えます。
 がん保険の一時金はいくらくらいもらえますか?
がん保険の一時金はいくらくらいもらえますか?
がん診断一時金(診断給付金)は契約時に金額を自由に設定できますが、金額を大きくすると保険料も高くなります。50万円〜300万円の範囲が一般的です。
 がん保険の一時金のメリットは?
がん保険の一時金のメリットは?
がん診断一時金(診断給付金)は、入院日数や症状・治療方法などによって必然と受ける金額が決まってしまう他の保障とは異なり、自分で自由に受取金額を選択できます。また、がんになったとき自由に使えるまとまったお金を受け取れる点は、がん診断一時金のメリットと言えます。
 医療保険とがん保険との違いはなんですか?
医療保険とがん保険との違いはなんですか?
民間の医療保険でもがんについて保障されますが、がん保険はがんだけに特化した保険です。がん保険と医療保険の違いは、主に、診断一時金の有無、入院・通院に関する給付金の内容、免責期間の有無があげられます。
年齢からランキングをみる
- 記載している保険料および保障内容などは2026年1月29日現在のものです。
- 保険料算出条件・保険商品について詳しくは、商品名をクリックしてください。
- 更新のある特約の保険料は更新時の年齢・保険料率によって決まります。
- 調査目的:保険の人気調査(申込数・保険会社遷移数をもとに算出)実施者:Sasuke Financial Lab株式会社 調査対象者:コのほけん!訪問ユーザー 有効回答数:77,407件 調査実施期間:2025年11月1日〜30日
- 商品改定やリニューアルの場合は前の商品の順位を引き継ぎます。
- お仕事の内容・健康状態・保険のご加入状況などによっては、ご契約をお引受けできない場合や保障内容を制限させていただく場合があります。
- 商品の概要を説明しています。保険商品の詳細は保険会社のウェブサイト、パンフレット、契約概要、注意喚起情報、ご契約のしおり・約款等を必ずご確認ください。また、表示された保険料は保険プランの一例です。前提条件(年齢や性別等)によって保険料は変わります。商品を選択される際には、保険料だけでなく、保障の内容等他の要素も含め総合的に比較・検討くださいますようお願いいたします。
- 「ネット申込」をクリックすると保険会社のページへ移動します。
- なお、専門家のコメントは当社からファイナンシャルプランナーに依頼し執筆いただいた原稿を、保険会社で了承のもと、当社で編集したものです。
- 口コミの内容は、ユーザーアンケートの回答内容に反しない範囲で、表現を整えた上で掲載しています。掲載しているユーザーの年齢はアンケート収集時の年齢であり、保険加入時の年齢ではありません。
- 「口コミ・評判」に掲載されている内容は、あくまでユーザー個人の主観的な感想や評価であり、保険商品の保障内容や保険料などを保証するものではありません。各ユーザーの前提条件(被保険者の年齢、性別、必要な保障条件など)によって、保障内容、保険料に対する評価も異なる可能性があるため、あくまでも参考情報としてご覧ください。
- 評点は、「総合満足度」、「加入手続きのスムーズさ」、「保険料の安さ」、「保障内容の充実度」、「顧客対応」、「保険金請求のスムーズさ」の各項目について、ユーザーが下記から選択したものを掲載しています。(いいと思う:5、少しいいと思う:4、普通:3、少しよくないと思う:2、よくないと思う:1)
- 「加入手続き」、「顧客対応」の評価には、ユーザーが保険商品を申し込んだ経路によっては、対象保険会社の商品を取り扱う保険代理店等に対する評価が含まれている可能性があります。
- 保険商品を選択する際には、商品の詳細を「パンフレット」、「契約概要」、「注意喚起情報」、「ご契約のしおり・約款」等にてご確認いただいた上で、保険料水準のみではなく、保障内容等も含め、総合的に比較・検討いただきますようお願いします。
- アンケート委託先のモニタ会員のうち、対象保険会社の対象の保険商品を契約された方に実施したアンケート調査であるため、コのほけん!経由で契約した方に限りません。














