がん保険は本当に必要か?種類・保険料の相場、加入のメリット・デメリットをFPが徹底解説!
この記事では、がん保険の必要性について、がん保険の種類や保険料の相場、加入のメリット・デメリットといった面から、ファイナンシャルプランナーが徹底的に解説します。
がん保険とは
がん保険とは、民間の保険会社が販売している医療保険の仲間のひとつで、病気の中でもがんに特化して保障する保険です。
医療保険とは違い、がん保険は契約後すぐに保障開始とならず、免責期間(待機期間)があり、免責期間(待機期間)は90日間であることが一般的です。
がん保険は主に次の4つの保障内容から成り立っています。
- がん診断給付金
- がん入院給付金
- がん通院給付金
- がん手術給付金
この他にも、以下のようながんに特化したたくさんの保障や特約を選ぶことができます。
- がん先進医療特約
- 放射線治療給付金
- 緩和療養給付金
- 保険料払込免除特約 など
(1)がん保険の給付金
がん診断給付金
がん診断給付金は、初めてがんと診断された時点で保険会社所定の条件を満たした場合に受け取ることができます。なお、保険会社によって「診断一時金」や「がん診断保険金」など、呼び方が異なる場合があります。
給付金の使い道は限定されておらず、入院費用にも退院後の通院費用にも使うことが可能です。また、がん診断給付金を受け取れる回数は「1回のみ」や「無制限」など、商品によってさまざまです。
関連記事:がん保険の一時金(診断給付金)はいくら必要?相場や所得税を解説します
がん入院給付金
がん入院給付金はがんの治療を目的に入院した場合に受け取れる給付金のことをさします。
受け取れる入院給付金の金額は、5,000円や1万円など用意された選択肢の中から設定します。
医療保険と異なり、万が一治療が長引いて長期入院になったとしても、全日数分の入院給付金を受け取ることが可能です。
がん通院給付金
がん通院給付金とは、がん治療のために通院した場合に受け取れる給付金のことをさします。
入院前後の通院で保障されるタイプ、通院のみで保障されるタイプなど保障の形態は保険の種類によっても異なります。
がん手術給付金
がん手術給付金とは、所定のがんの手術を受けた場合に入院給付金とは別で受け取れる給付金のことをさします。
金額は「がん入院給付金日額の10倍」や、「がん入院給付金日額の〇倍」で決められています。
手術の回数には一般的に制限はありませんが、一部の商品には「何日に一回まで」という条件を設けている商品もあります。
(2)がん保険の特約
がん先進医療特約
先進医療とは、厚生労働大臣が認定する最新の高度医療技術のことをさします。
この特約は通算1,000万円~2,000万円を上限とし、かかった技術料を実費で保障するタイプが主流になっています。
なお、がん保険に付帯する先進医療特約の場合、「がんの治療を目的とした先進医療」にのみ適用される点は注意が必要です。
女性がん特約
女性がん特約とは、女性特有のがんによる入院・手術等の際に保障される特約です。
乳房の切除術や子宮・卵巣の全摘手術を受けた時に給付金が支給されます。また、乳がん手術を受けた後の「乳房再建術」を受けた際にも、同様に給付金が支給されるタイプもあります。
緩和療養特約
緩和療養特約とは、がんによる痛みを和らげる治療や緩和ケアのために入院、あるいは在宅医療を受けた時に緩和療養給付金が支給される特約です。
がんによる痛みを和らげる目的で疼痛緩和薬(とうつうかんわやく)や神経ブロック等を使用した際などに、入院・通院・在宅のいずれの方法でも保障されます。
保険期間や給付金の額は保険ごとに異なるものの、保険期間が終身タイプの特約もあり、支払いは月ごとに1回、保険期間を通じて24回等の支払い上限が設定されるのが一般的です。
がんの罹患率と死亡率
国立がん研究センターの調査によると、日本人が生涯でがんと診断される確率は、以下の通りです。
- 男性65.5%(2人に1人)
- 女性51.2%(2人に1人)
また、男女でがんで死亡する人の多い部位も異なっていて、男性では肺や大腸、胃が多い一方で、女性は大腸や肺、膵臓が多いという結果も出ています。ただし、死亡する人が多い部位と罹患しやすい部位は異なり、罹患する人の多い部位は男性では前立腺や大腸、胃であるのに対し、女性は乳房や大腸、肺が多い結果となっています。
関連記事:がんとはどんな病気?生存率や入院日数のデータからがんの実態を知ろう
がん保険の加入率
公益財団法人生命保険文化センターの調査によると、がん保険・がん特約の加入率は39.1%でした。
性別ごとの加入率を見ると男性は38.0%・女性は40.0%と、女性の加入率が高く、性別を通じて40代女性の加入率がもっとも高くなっています。
がんの治療費
がんの治療費は高額になりがちで、がんの部位や範囲、進行具合によって治療方法は異なり、かかる治療費にも差が出ます。
高額な治療費には健康保険の「高額療養費制度」などの社会保険も利用できますが、それを差し引いても家計にかかる負担は大きくなる傾向にありますので、預貯金に大きな余裕がない場合にはやはりがん保険への加入を検討することが必要になってきます。
関連記事:高額療養費制度は医療費がいくら以上から使える?さらに負担を軽くする多数該当、世帯合算とは?
がん治療における公的医療保険制度の対象外の費用
差額ベッド代
差額ベッド代とは、大部屋より人数が少ない部屋を選択した際に発生する室料のことをさします。
利用する病院ごとに1日あたりの差額ベッド代は大きく変わるため、数日の入院であれば負担は少なく感じますが、長期入院になった場合は負担が大きくなります。年齢を重ねるごとに入院が長期化する傾向にあることから、個室等への入院を希望する場合は、がん保険を検討することをおすすめします。
そのほか、入院中に発生する治療以外の生活全般の費用に関しては公的医療保険ではカバーされません。
関連記事:差額ベッド代をわかりやすく解説!医療費控除や高額療養費は適用される?
先進医療の技術料
先進医療の種類によってかかる技術料はさまざまです。
仮に、1ヶ月の医療費が200万円かかったうちの100万円が先進医療であった場合、公的医療保険の対象になるのは先進医療以外の100万円の70%のみです。
一部自己負担分については「高額療養費制度」が適用されますが、先進医療の技術料には高額療養費は適用されません。
関連記事:先進医療とは?医療保険でカバーできる治療や注意点、先進医療の代表例を紹介
自由診療の治療費
自由診療は、厚生労働省の認可が下りていない治療法や薬を使用する医療行為で、保険が適用されない診療にあたります。
自由診療と先進医療の違いは「本来は健康保険が適用されて自己負担が3割になる部分の治療も含めて全額が自己負担になる」という点です。
自由診療を選択することで治療の選択肢が増え、「国内では未承認でも海外では承認済み」等の最先端治療を受けることも可能ですが、公的医療保険の対象外のため、かかった治療費は全て患者の負担になります。
関連記事:健康保険適用になる診療・ならない診療 保険適用外診療の対処法
がん保険が必要な人・不要な人とは?
がん保険が必要な人は、がんによる入院や手術の費用を手厚くカバーしたいと考えている人です。医療保険でもがんに対する保障は可能ですが、がんに特化したがん保険のほうが、より手厚い保障を受けることが可能です。
医療保険の場合は支払い日数が60日や120日などの制限が設けられていますが、がん保険には支払限度日数が設定されていない保険が揃っています。長期入院に備えたい人も、がん保険を検討するのがおすすめです。
がん保険がいらない人とは、万が一がんにかかった際の治療費をご自身の貯蓄でまかなえる人です。
しかし、治療の長期化などで、数千万以上の自己負担額が発生する可能性もあるため、貯蓄があってもがん保険への加入を検討することをおすすめします。
まとめ
以上の内容をふまえ、最後にがん保険のメリット・デメリットをまとめます。
がん保険のメリットは以下のとおりです。
- 入院給付金は日数の限度が無い
- がん診断時に一時金を受け取ることができる
- 先進医療特約で最新の治療法も選択できる
- 受け取った保険金や給付金は基本的に非課税である
がん保険の保険金や給付金は基本的には非課税ですが、生存給付金のような「祝い金」については所得税や住民税がかかる可能性があります。
また、非課税で受け取った給付金が相続財産として遺族に引き継がれるような場合には、相続税の課税対象となることもありますので覚えておきましょう。
一方で、がん保険のデメリットは以下のとおりです。
- がんに対する治療のみを保障対象としている
- 皮膚ガン(上皮内新生物)の一部は保険の対象にならないものもある
- 契約後には90日間の待機期間(免責期間)がある
- 公的な健康保険でも対応できる場合がある死亡保障が少ない
.jpg)
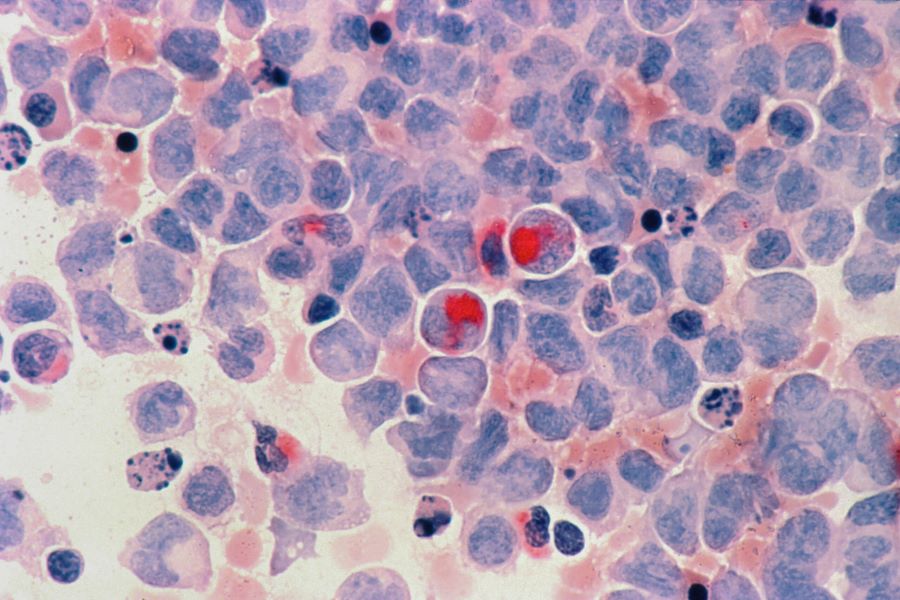


.jpg)
.jpg)
![女性特有の病気に備えたい方におすすめ!オリックス生命の医療保険CURE Lady Next[キュア・レディ・ネクスト]人気の理由を大調査](https://images.microcms-assets.io/assets/f84aa30f91624818a0311521de70d1bb/06f46e9d2e1c47f1a4f7b229c50ad686/AdobeStock_334906465%20(1).jpg)
.jpg)
.jpg)


