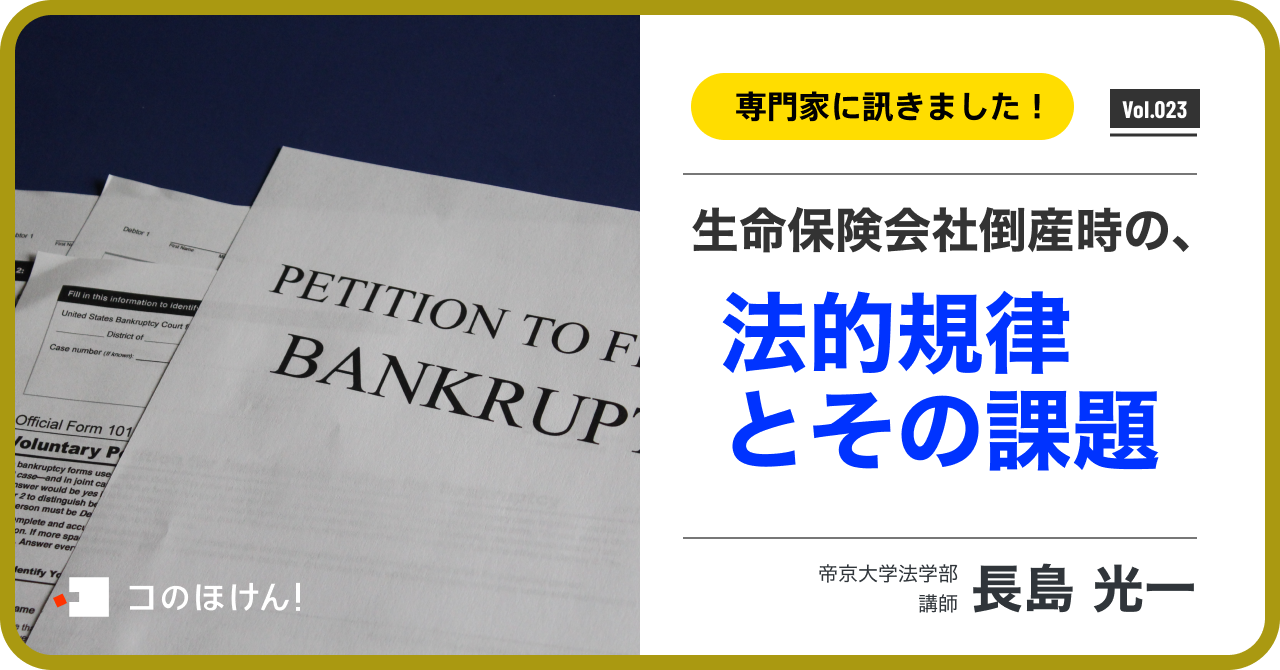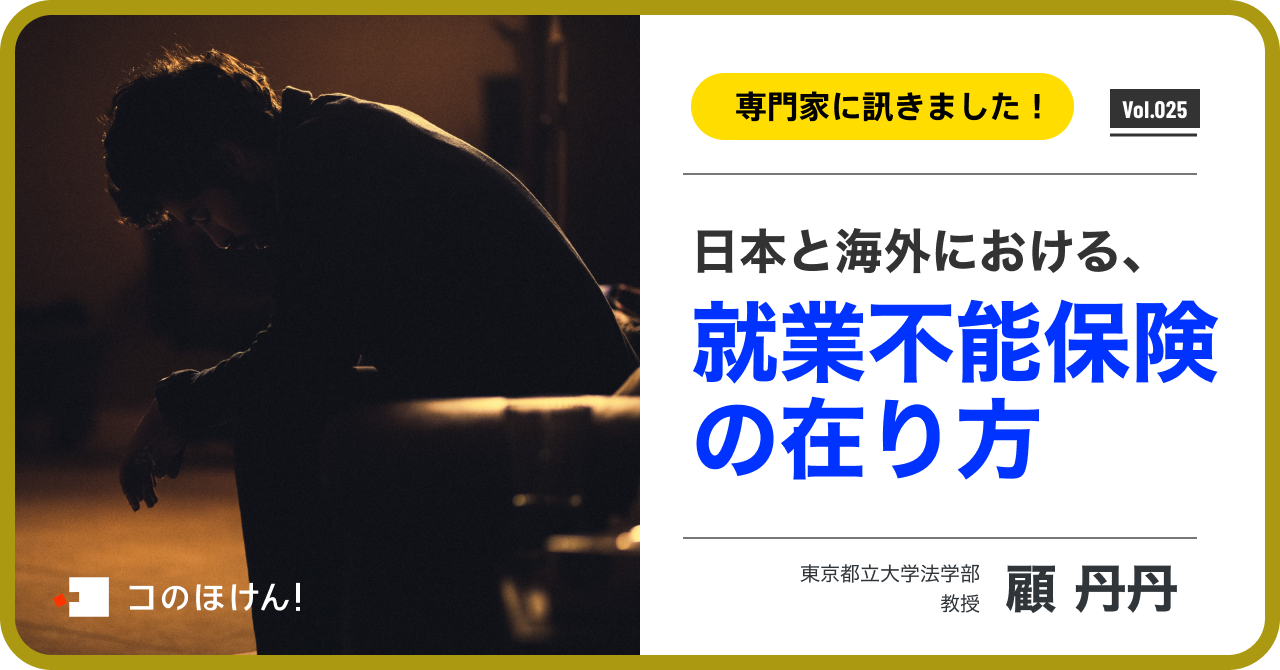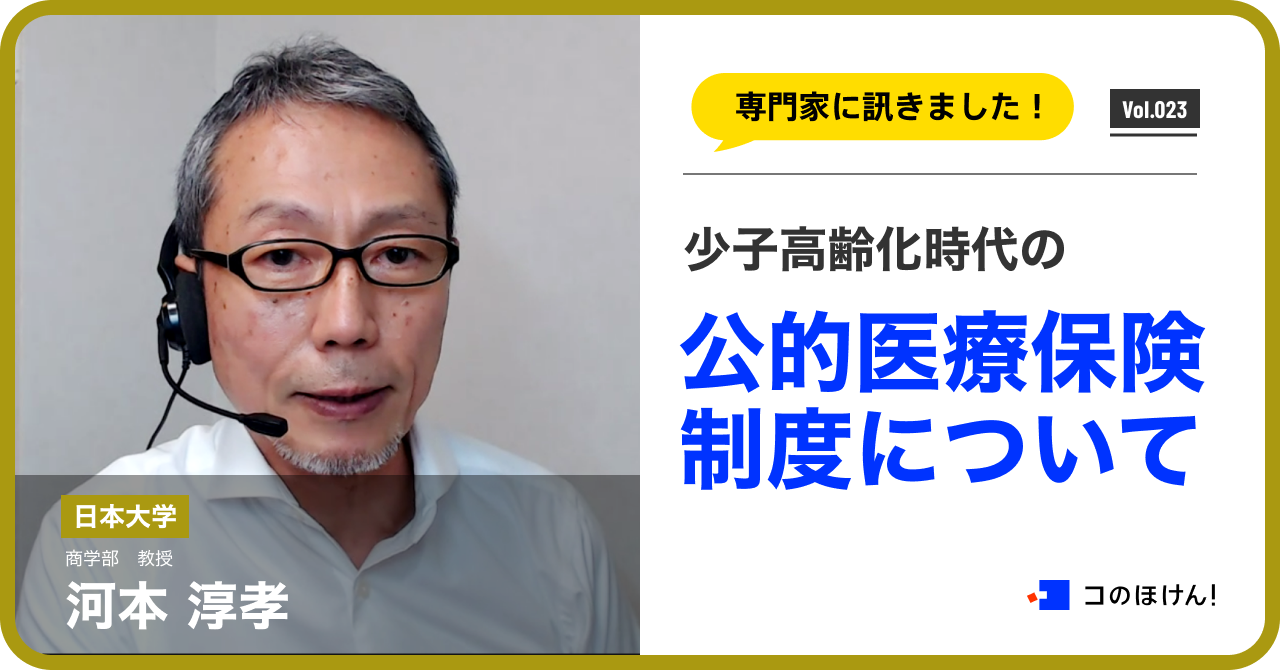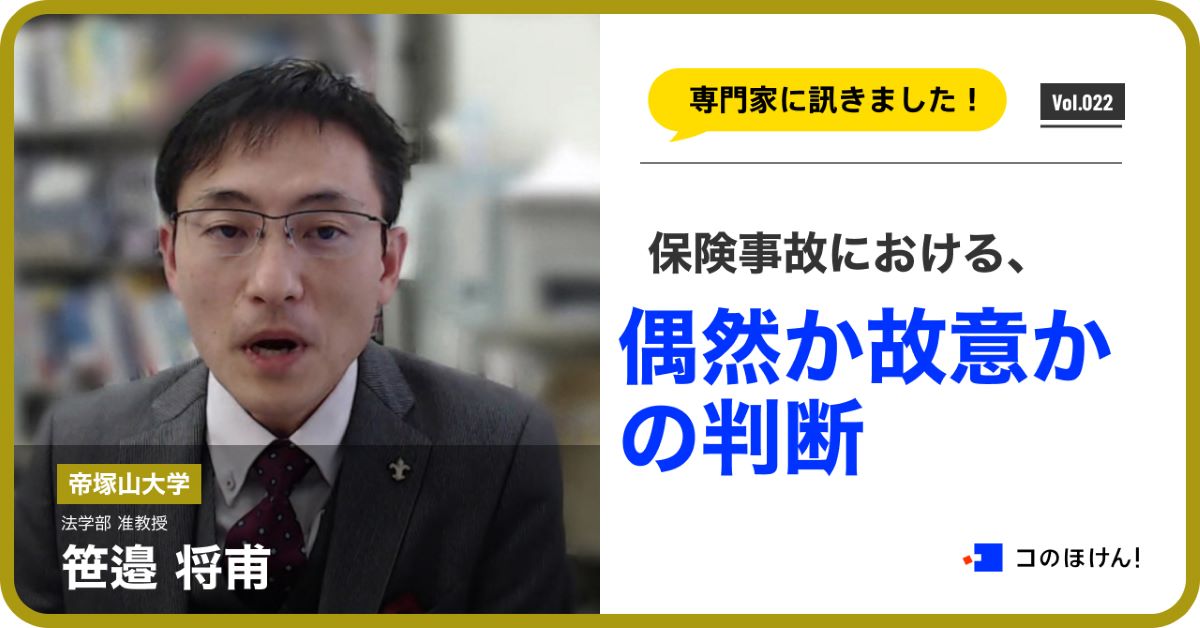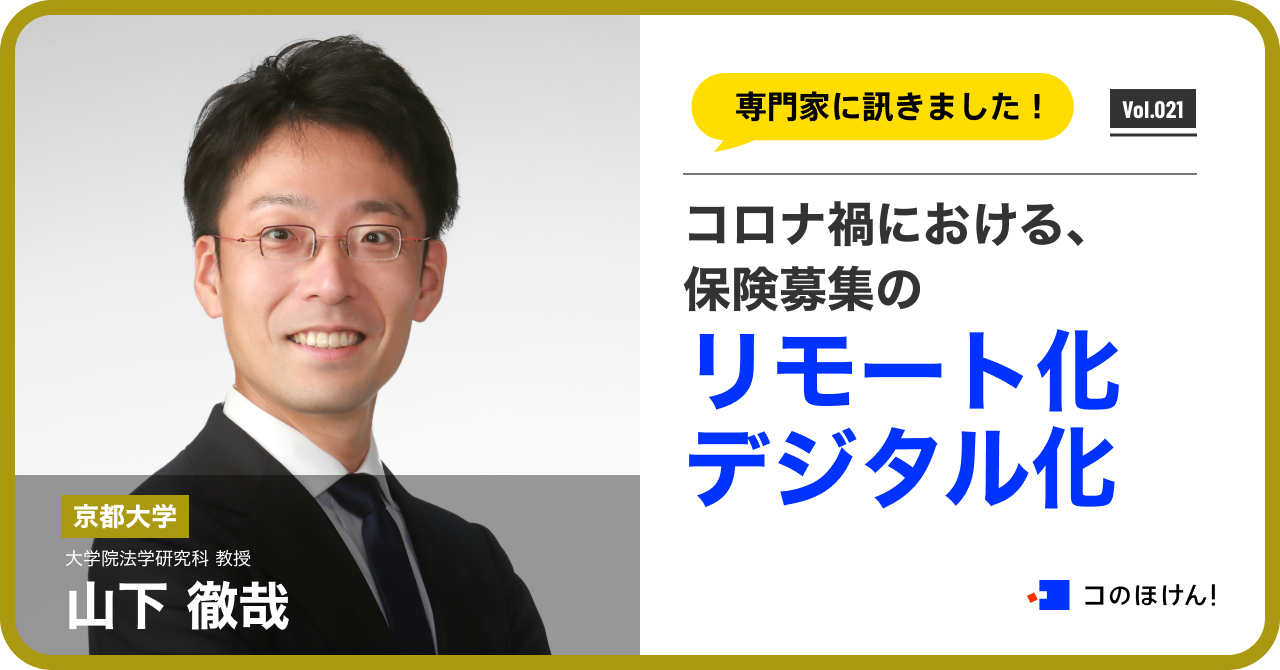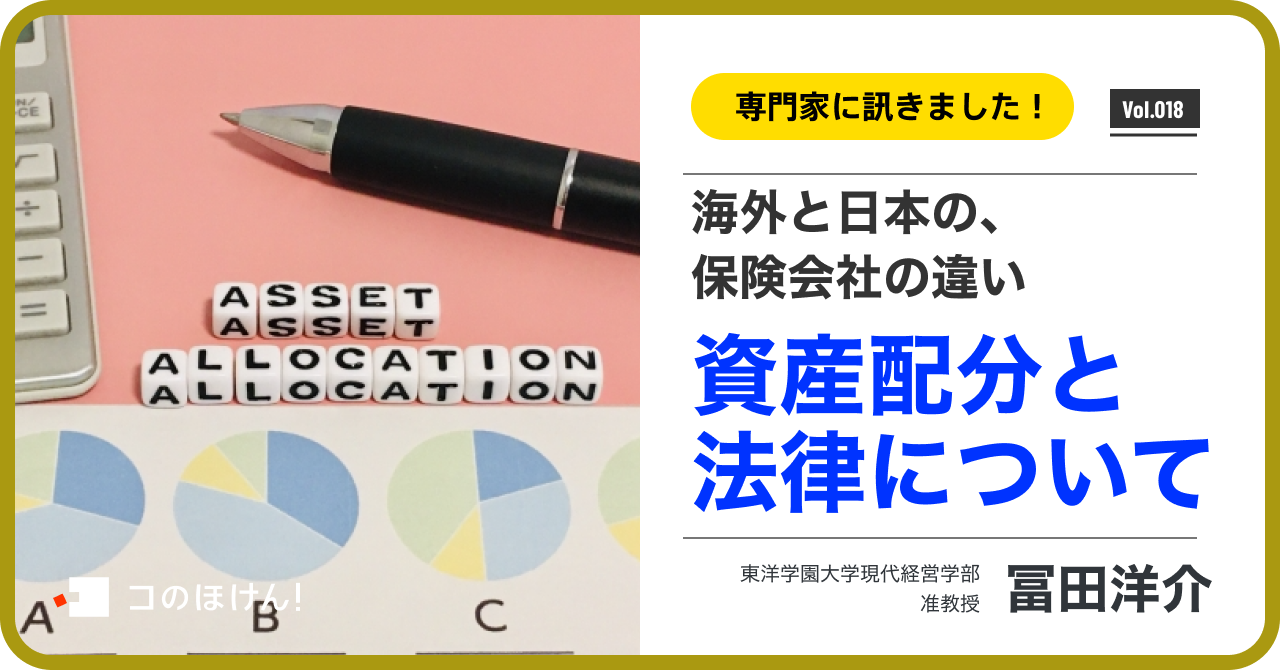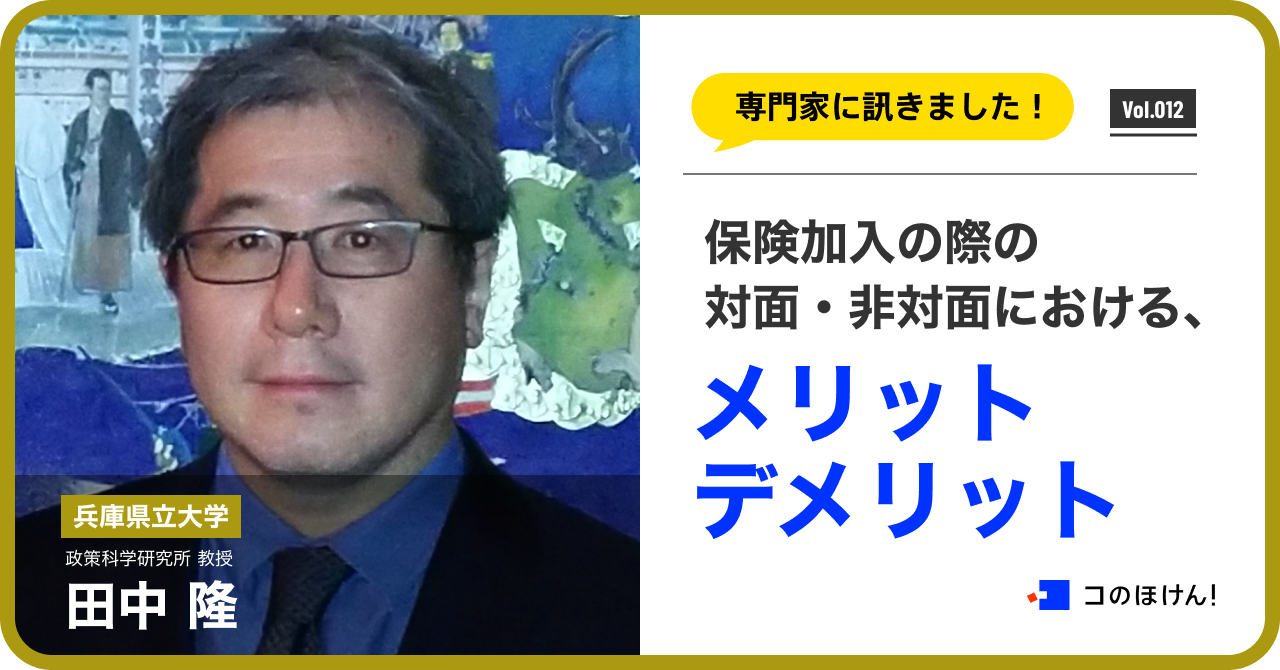
保険加入の際の対面 ・非対面におけるメリット・デメリット|マーケティング視点から
今の専攻を志されたきっかけは何ですか?

先生にとって、保険を一言で表現すると、どのようなものでしょうか?

言い換えると、生命保険(死亡保険)は、「純粋贈与の目的」で利用される「最も経済合理的な商品」です(それ以外の多くの保険商品は、「自己に関する利益を守る目的」で利用される「最も経済合理的な商品」です)。
純粋贈与=見返りを求めていない増与
コのほけん!編集部

生命保険においては募集や加入等において関連する要素が複雑なので、それらの分析に大きな魅力と喜びを感じたことです。例えば、経済合理的だと自任する死亡保険の加入者が、保険会社に対して経済合理的な考えで「市場」のサービスである生命保険を「契約」しても、家族に対しては「(純粋)贈与」することを意図して加入します。すなわち加入者自身は、自身の死亡後の家族の生活保障を考えて、見返りを考えることなく生命保険に加入する構図になります。この純粋贈与とは主に、元明治大学・現千葉工業大学の中沢新一先生をはじめ、元京都大学・現佛教大学の矢野智司先生が指摘、展開されてきましたが、「見返りを求めない贈与」というものです。
家族を中心に展開される純粋贈与の構図を確認すると、1人の加入者には、保険会社や市場に向けた「経済合理的な一面」と自身の家族に向けた「純粋贈与の一面」という、二つの異なる面があります。加えて、生命保険(販売)と消費者に焦点を当てた研究が少数である一方で、これらの研究が、社会的に、色々な方面で、意義をもたらすのでは、と感じていたことも、大きな魅力でした。
純粋贈与についてわかりやすく例えると、ビジネスの現場であれば、損得を考えて行動することが多いと思いますが、しかしながら日常生活の中で、自分のご家族、もしくは子供さんに関しては、損得を考えたり、見返り求めることは少ないと思います。子供さんがどのように成長しようが、親御さんはそれとは関係なく与え続けますよね。まさに、この姿勢は見返りを求めていません。これが純粋贈与です。愛情の「核」でもあり、「根源」とも言えるでしょう。
マーケティング視点からの対面・非対面のメリット・デメリットとは?
コのほけん!編集部

対面と非対面のメリットとデメリットは、以下の通りです。
今後のマーケティングにおいては、対面と非対面のハイブリッド化が進行する可能性も高いと思われますが、企業や組織等におけるAI等の普及によって、非対面の割合が増大していくことになります。
【非対面のメリット】
企業や組織等にとって、物理的制約や費用等を含めた総合的な観点でのコストが削減、合理的な資源活用と費用対効果が期待できること。効率的に、多くの情報「量」と「手数」を消費者や加入者に提供でき、消費者に対する広い「面」の部分での大きな効果を与えられること。
【非対面のデメリット】
従来的なリレーションシップマーケティングのような個の消費者レベルでの「深さ」と「角度」の部分での浸透効果が限定的であり、顧客ロイヤルティーの深化が簡単ではないこと。ただ、進行形のリレーションシップマーケティングの発展と共に、AIとオンラインツールの普及が上記の「深さ」と「角度」の問題を改善させていく可能性がある。
【対面のメリット】
消費者から人間性や信頼性、雰囲気等を実感されながらの活動になるので、従来的なリレーションシップマーケティングのような消費者レベルでの「深さ」と「角度」の部分での浸透効果が高く、顧客ロイヤルティーのさらなる深化が望めること。
非対面の割合が増大する中で、この「深さ」を創り出す対面の重要性・非日常性が増すことになるが、生保商品のような商品に加入する際には、この「深さ」からの発展が非常に強力であること。
【対面のデメリット】
企業や組織等にとって、物理的制約や費用等を含めた総合的な観点において、合理的な資源活用を追求することが難しくなることと共に、目標達成に至らなかった際の(含心理的)コストは、非対面時より大きいこと。
多くの情報「量」と情報の「手数」を消費者や加入者に効率的に提供することには限界が生じ、消費者等に対する広い「面」の部分での効果も限界があること。
上述の対面のメリットや質問5の箇所でも言及していますが、今後の流れとしては、非対面が日常的になり、対面が非日常的なものになる可能性が高いと思います。一方で、対面が非日常になることでさらなる付加価値がつき、対面の魅力が増していく可能性もあります。
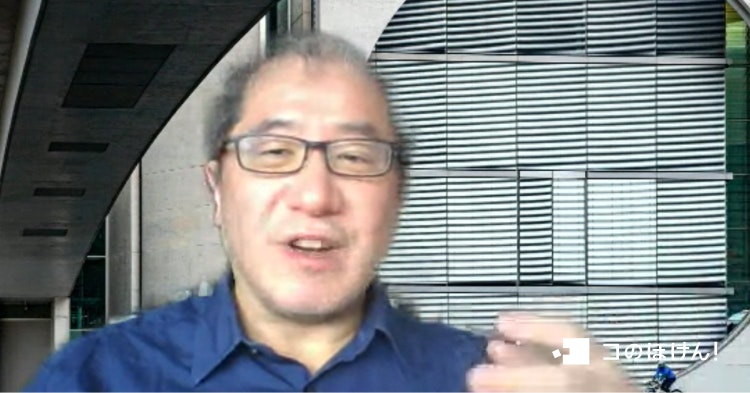
信頼できるFPや営業職員の見極めるポイントとは?
コのほけん!編集部

募集人の方々、FPの方々も含めてですが、彼・彼女たちのメリットにならない(新規契約につながらない)ことでも、嫌な顔をせずに、消費者が納得するまで、誠実に相談や説明に時間を割いてくれる姿勢です。彼・彼女たちの得にならないことに対して嫌がるか、関係なく誠実に対応してくれるのか、という姿勢は大きなポイントだと思います。
こういった姿勢・コミットメントにおいては、自分の利益に拘らない非打算的姿勢と誠実さに、質問1等でも触れた「純粋贈与」が含まれています。このような姿勢から、消費者の利益を軽視して自分達の利益を重視するのか、あるいは消費者の利益を重視するのかについて、見極めることができます。特に、保険商品に関する知識に自信の無い消費者にとっては、重要なポイントです。このことは、言い換えれば、非打算的姿勢と誠実さを有する募集人は、時間がかかってもトップセールスになり得るとも言えます。
加えて、彼・彼女たちが募集している保険商品のメリットだけでなく、デメリットも明確に説明していることも、重要なポイントです。これらは、彼・彼女たちの募集人としての能力と誠実さを表しているからです。
非対面(オンライン)で生命保険に加入する場合の注意点とは?
コのほけん!編集部

ネット生保での観点となりますが、ネットでの生保加入の作業では、安い保険料の代わりに、予め保険に関する知識や情報を得ていることが必要なので、消費者に見えにくい(学習にかける)コスト負担を求めるものでもあります。
注意すべき点は、色々な識者や専門家の方々が指摘されていると思いますが、以下の通りです。
①加入目的の明確化、自身のライフプランの各場面での保障の明確化、
②対応する各保険商品の保障内容とメリットや(特に)デメリットの確認、
③見慣れない重要事項説明書や保険約款等、保険商品ならではの専門用語に加えて、事務処理手続き等に関する理解・確認、
①はネット生保では、加入の際に、明確化されている方が比較的に多いかもしれません。
②は、加入しようとしている保険の保障内容でメリット・デメリットを把握する必要があります。特に、どこまでが保障の範囲で、何が保障できないのかはしっかりと確認しておきたい部分です。
②と③に関しては、見慣れない部分があるとは思いますが、契約に関する作業の際には、重要事項説明書や保険約款等をしっかりと読むことです。
また①~③については、生命保険文化センター等のHP上に生命保険や生活設計に関する解説等があるので、それらから生命保険や専門用語等に関する理解を深めるのが良いと思います。③では、事務手続きの中で何の書類が必要になるか等の理解と確認が重要になってくると考えています。
①~③に対応する保険に関する知識や情報を得る作業をきちんと行わないと、色々な識者や専門家の方々も指摘されていると思いますが、以下の④~⑥の心配が現実になることもあります。
④告知情報の記入にミス等が生じる可能性。審査が厳しいとされるネット保険において注意すべき点ですが、場合によっては、ご家族によるミスのチェックも一案です。
⑤保障内容に関する誤解や誤認が起きる可能性。自分のイメージしていた保障内容と契約後に確定した保障内容にズレが生じたり、ネット生保等であるのにも関わらず余計な保険料を支払う可能性があります。
⑥必要書類提出の締切日超過、必要書類の不備等による、再度の加入手続き作業を強いられることもあり得ます。
ネットでの契約の際に、事前に理解していた方が良い情報について、上述の①~③に関する知識や情報は大事ですが、それらに加えて、社会保険制度や予定利率、貨幣価値に影響を与える社会経済情勢に関する情報や知識等があげられます。
④~⑤の心配を防ぐために、消費者が負担する見えにくいコストとは、社会経済情勢や自身のライフプランに対する分析・計画等といったやや抽象的な作業(学習)から、各保険商品の保障内容や保険料に対する比較・検討といった実体的な作業(学習)に費やされるものとなります。生保加入の作業に取り組む前に、それらのコストの負担を苦痛と思わずに作業することを自身で確認することが(もしくは楽しむか、ご家族との共同作業とするか)、まず重要です。
一番良くないことは、この辺の作業(学習)への確認をあやふやにして、作業(学習)へのコストをかけずに、契約に関する作業にとりかかることです。この場合には、契約に関する作業を進めながら、途中まで時間等をかけてコストがかかってしまったので、(心理的・時間的に)引き返せない、再検討できないという状態になってしまい、「まあいいや、契約しよう」と、うやむやのままで契約してしまうことが、起こり得ます。
加えて、ネットでの加入作業においては、要所要所、そして最後までの確認や検討の作業が重要ですが、作業において不安を感じる場合、保険相談窓口に相談して、FP等の専門家のサポートを受けることも必要となります。
生命保険業界の販売チャネルの展望とは?
コのほけん!編集部

販売チャネルの主流について、予想は難しいですが、販売チャネルにおける対面と非対面のハイブリッド化が、一層進んでいきます。対面と非対面のそれぞれメリットを取り入れたり、デメリットを補う形でハイブリッド化が進んでいきます。
昨今の傾向から、増加しているのは代理店チャネルですが、直近は伸び悩んでいるようでもあり、様子を注視したいと思います。近年、代理店チャネルが好まれてきた理由は、消費者の自己選択がある程度確保されていることに加えて、消費者に見えにくいコスト負担が少ない(質問4)対面販売チャネルであることが考えられます。
Z世代と呼ばれる世代以降が生産人口のマジョリティとなると、長期的には通信販売が拡大していく可能性もあります。しかし、生保契約締結における情報(と知識)の非対称性等の環境に加えて、ネット生保では、上述のコスト負担が伴うことから、何処まで拡大していくかは不透明です。その一方で、カスタマーセンターの設置等を行うネット保険会社に見られるように、非対面チャネルにおいても、非対面の弱点を補う対面的要素が加えられたハイブリッド化が進んでいるとも言えます。
コロナ禍により、企業も消費者もオンラインツールの積極的な活用を覚えました。大きな可能性を秘めているのは、「バーチャル対面」とも言うべきオンラインツールの活用による非対面化を打ち出す動きです。この動きには、募集側と消費者側の物理的な制約を和らげ、消費者に見えにくいコスト負担を和らげることから、双方のコスト面で大きなメリットがあります。この動きは、「バーチャル対面」としての対面的要素を伴った非対面化の進行とも言える一方、対面と非対面のハイブリッド化の一つの現象とも言える可能性があります。
近年の減少傾向が持ち直す向きもある営業職員チャネルですが、前述の生保契約締結における情報(と知識)の非対称性等の(対面販売チャネルに基本的に有利な)環境は今後も変わらないので、最大の割合を保ったまま、存続していく可能性があります。そして、代理店チャネルや営業職員チャネル等において、前述した「バーチャル対面」としての非対面化の動きが組み込まれていく可能性があります。
販売チャネルにおけるハイブリッド化の中で、今後の販売等におけるプロセスと方向性については、非対面が日常化する方向となり、対面機会が非日常化する方向となっていきます。言い換えますと、対面の機会は減る一方で、非日常化による重要性が増すことにもなり、対面の際の要領等に加え、対面の瞬間や時間、空間等の重みが増すことになります。
今後の生命保険業界の展望としましては、以下のような展開が考えられます。
現在、人生100年時代が謳われる中、生保業界がInsurTechを活用していくことは当然重要ですが、生保業界・生保企業は、各業界の垣根が薄れるX-Techでの競争環境に位置づけられることになります。X-Tech下での生保業における医療・ヘルスケアに関するInsurTechの活用が最も有望な方向となり得ますが、MedTech・HealthTechの進展の中、巨大IT企業等を含む全ての産業にとっても、最も有望な方向となります。
生命保険業は今後も重要となるものの、従来からの生命保険企業の専売特許でなくなっていく可能性があります。X-Tech下の生保企業にとっては、従来的な生保サービスに拘らずに、「消費者ニーズの絶対性」と「消費者ニーズの延長線上での生保業」という視点を軸とした、持続的イノベーションだけではなく、特に「破壊的イノベーション」の創出が、戦略的に、死活的に、重要となります。
まとめ(編集部後記)
マーケティング視点から見た、保険加入の際の対面 ・非対面におけるメリット・デメリットについてお話を伺ってきました。
販売チャネルにおける対面と非対面のそれぞれメリットを取り入れたり、デメリットを補う形でハイブリッド化が進んでいくというお話を伺い、保険代理店としてどんなサービスを提供できるのか、考えていきたいと思いました。




.jpg)