40代でもがん保険は必要!その理由と40代女性・男性におすすめの選び方を解説
いまや日本人の「2人に1人ががんになる」と言われる時代。そんな中で、「がんは年を取ってからの病気」と思い込んでいませんか?
実は、まだまだ働き盛りの40代でも、がんに罹患する可能性は十分にあります。仕事や子育て、住宅ローンなど、何かと出費の多いこの世代で病気に見舞われると、経済的な負担は予想以上に大きくなることも。
この記事では、40代におけるがんの罹患率や、治療にかかる費用の目安を紹介しながら、男女別におすすめのがん保険の選び方も解説します。「今の自分にがん保険は必要なのか?」と不安に感じている方に向けて、保険選びのヒントをご提案します。ぜひ最後までチェックしてみてください。
この記事のポイント
- 40代でもがんにかかる可能性は十分にあり、特に乳がんや大腸がんなど特定のがんの罹患率が高まる年代である。
- がん治療には高額な費用がかかる場合があり、働き盛りの40代では収入減少や退職のリスクもあるため、備えが必要である。
- 治療費の自己負担額が軽減できる制度もあるが、それでもがんによる経済的負担は大きい。40代は、自分に合ったがん保険を検討するのがおすすめ。
40代にがん保険は必要か?罹患リスクから見る必要性

40歳以降にがんにかかる確率は?
国立がん研究センターの調べによると、各年代のがん罹患率は30代後半から上がり始め、40代後半からさらに上がり始めます。
男女ごとに見ると、男性のがん罹患率は40代後半から上がり始め80代以降でピークを迎えるのに対して、女性は20代後半から上がり始め90代後半でピークを迎えるのが特徴です。
罹患する部位で見ると、40代男性では胃がん・大腸がん(結腸がん・直腸がん)・肝臓がんなどの消化器系のがんの罹患数が多くを占めており、特に大腸がんに罹患する割合の多さが際立っています。
胃がんの罹患率は40代後半から80代まで上がり続け、ピーク時には人口10万人あたり約450人にもなります。
40代女性では乳がん・子宮がん・卵巣がんの罹患が多くを占めており、特に乳がんの罹患率の高さが際立っています。
2021年の調査では乳がんの罹患率は40代から急激に上がり、40代後半では人口10万人あたり約240人となります。
ちなみに、同調査では乳がん罹患率のピークは70代後半で、そのピーク時には人口10万人あたり約270人にもなっていました。
がんが治る確率は?
がんが治る確率として「5年相対生存率」という指標があります。
5年相対生存率とは
なんらかのがんと診断された場合に、治療でどのくらいの患者を救えるかを示したもの。あるがんと診断された人のうち5年後に生存している人の割合が、日本人全体で5年後に生存している人の割合に比べてどのくらい低いかで表す。
この5年相対生存率は、100%に近いほど治療で命を救うことができるがんであり、逆に0%に近くなるほど治療では助かる見込みが低いがんです。
例として、40代男性が罹患しやすい胃がん・大腸がん・肝臓がんの5年相対生存率を見ると、大腸がんが一番治る確率が高いがんであることがわかります。
40代男性が罹患しやすいがん | 5年相対生存率 |
|---|---|
胃がん | 67.5% |
大腸がん | 71.7% |
肝臓がん | 36.2% |
また、40代女性が罹患しやすい乳がん・子宮がん・卵巣がんの5年相対生存率を見ると、乳がんが圧倒的に治る確率が高いがんであることがわかります。
40代女性が罹患しやすいがん | 5年相対生存率 |
|---|---|
乳がん | 92.3% |
子宮がん | 78.7% |
卵巣がん | 60.0% |
このように、がんの部位ごとに治る確率は大きく異なっています。
40代ががんにかかったら…経済的リスクから見るがん保険の必要性
40代でもがんにかかる可能性は十分にあることが分かりましたが、もし実際にがんになってしまったら、治療費はどのくらいかかるのでしょうか?
次に、がん治療のおおよその費用と、がん患者の就労状況について見ていきます。
がん治療にかかる平均自己負担費用と入院日数
ここでは、代表的ながんの種類別に、平均的な自己負担費用額や入院日数について解説します。
例① 胃がんの場合
たとえば40代男性に多い「胃がん」を患った場合、腹腔鏡手術だと開腹手術と比較して治療費が若干高くなります。
治療にかかる入院の平均日数は10日ほどで、治療費の目安は入院・通院合わせて約130万円となりますが、高額療養費制度を利用することで、自己負担額を抑えることができます。
高額療養費制度とは
医療機関や薬局などで支払う金額が自己負担限度額を超えた場合に、その超えた金額分が後で払い戻される制度。
70歳未満の一般的な年収区分(約370~770万円)だと、1か月の自己負担限度額は「80,100円+(医療費-267,000円)×1%」となり、これを越えた金額が高額療養費制度によって払い戻されます。
もし治療費が約130万円かかった場合、一般世帯で70歳未満だと1年目の自己負担額は約11万円となります。
関連記事:高額療養費制度は医療費がいくら以上から使える?自己負担額の引き上げ決定で今後どうなる?さらに医療費の負担を軽くする制度も紹介!
例② 乳がんの場合
女性に多い「乳がん」の場合、乳房温存手術に加え、術後の予防抗がん剤・放射線治療・ホルモン療法などの治療法を行います。乳房切除術と乳房再建(インプラント)を同時に行うこともあります。
なお、以前は全額自己負担だったインプラントは、2013年より保険適用となったため自己負担額を抑えることができるようになりました。
治療にかかる入院の平均日数は温存手術で7日ほど、入院・通院合わせて約215万円の治療費がかかります。
ですがこのケースでも、高額療養費制度を利用することで自己負担額を抑えることが可能。この場合、一般世帯で70歳未満だと1年目の自己負担額は約53万円となります。
関連記事:がんの治療費と自己負担額は平均でいくら?手術や抗がん剤治療などの治療別に解説
がん治療で退職・解雇される人も
厚生労働省の調べによると、がんの治療のために仕事をしながら通院している患者は全国で約32万5,000人います。
これは、あらゆる規模の企業に共通していることもわかっています。
その中でも約70%の人が仕事と治療の両立に対して「難しい」と感じていて、実際に会社で働きながら治療を受けていた人の34%が依願退職もしくは解雇されています。
なお、自営業者でも13%の人が廃業に追い込まれているようです。
がん患者の収入の変化を見てみると、がんと診断されてから今までと職業が変わったり、職業が変化したことが原因で収入が下がった人は全体の22%。19%の人は、無収入になっています。
また、がん患者の平均年収も、がん診断前の約395万円から診断後の約167万円となっており、大幅に減少していることが分かります。
前述の5年相対生存率を見てもわかるように、治るがんが多くなってきた反面、仕事とがん治療の両立はまだまだ難しいのが現状です。
そのため、万が一がんを患ったら、多くの人にとって経済的な問題が出てくることを覚えておきましょう。
関連記事:がんで働けなくなったらどうする?治療と仕事は両立できる?治療費を軽減する公的保障制度を知っておこう!
40代でもがん保険は不要と言われる理由
一度がんに罹患すると、治療費や収入減のリスクがあることがわかりましたが、それでも働き盛りの40代に「がん保険は不要」と言われることがあります。
その理由は、
- 高額療養費制度
- 傷病手当金
- 公的介護保険
などの公的保障があるからです。
高額療養費制度は先述したとおり、医療費支払の自己負担を軽くする制度です。
傷病手当金とは
病気やケガで3日以上就労不能な状態が続いている場合、欠勤4日目から1日につき標準報酬日額の3分の2が最長1年6か月にわたり受け取れる制度。
公的介護保険とは
40歳以上の人が介護が必要になったときに受けられる介護サービスの自己負担額が、1~3割に軽減される制度。※自己負担額は所得に応じて異なります。
公的介護保険では、認知症だけではなくがんを含む特定疾病の認定でも、介護サービスを利用することができます。
このような公的保障があることで「がん治療にかかるお金や生活費、介護にかかるお金には心配がいらない」と考え、がん保険は不要と言われることがあります。
しかし公的保障では、全ての費用をまかなえる訳ではありません。
保障が受けられる期間や金額には限度があり、がん治療中には公的保障適用外の全額自己負担しなければならない費用が発生することもありますので、注意をしましょう。
その点、がん保険に加入していたら給付金が受け取れるので、お金の心配をすることなく治療に集中することができますね。
関連記事:傷病手当金とは?退職したらもらえない!?退職後の支給条件や計算・申請方法を解説
40代におすすめ!がん保険の選び方
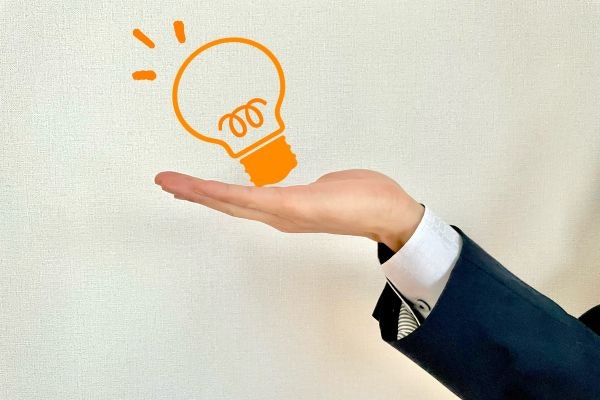
生命保険文化センターの調査によると、40代男性のがん保険およびがん特約の加入率は52.8%と全世代の中で最も高く、女性の場合でも40代が全世代の中で最も高い加入率(49.2%)となっています。
男性・女性ともに、多くの40代が加入するがん保険。ではどうすれば、様々なリスクをカバーできるがん保険を選ぶことができるのでしょうか?
40代男性のがん保険の選び方
がんに対する保障は、
- がん保険
- 医療保険にがん特約を付加する
の2パターンから備えることができます。
医療保険にがん特約を付加する場合、がん保険に加入するよりも保険料が安いメリットがありますが、がんに対する保障はがん保険よりも手薄く、医療保険を解約してしまうとがん特約も消滅してしまうデメリットもあります。
40代男性が罹患しやすいとされている、胃がん・大腸がん・肝臓がんのリスクを幅広くカバーしたいのであれば、医療保険ではなく保障内容ががんに特化している「がん保険」に加入するのがおすすめです。加えて、死亡保障など総合的に判断して保険料とのバランスも考えましょう。
がん治療では、入院治療以外に通院治療の期間も長くなります。保障には「通院保障」があるものを検討しましょう。
また、収入減による生活費の補てんという面を考えれば、がんと診断された際にまとまったお金を受け取ることができる「がん診断一時金(診断給付金)」があるタイプもおすすめです。
保障期間は、がんの罹患率が50代以降になるほど上昇していくことを考えると、保障が一定期間のみの定期型よりも一生涯保障が続く「終身型」が良いでしょう。
保険料を少しでも抑えたいのであれば、解約返戻金がない「掛け捨てタイプ」を選ぶと保険料の負担を軽くすることができます。
関連記事:掛け捨て型がん保険はもったいない?貯蓄型との違いや掛け捨て型がおすすめの人を解説
40代女性のがん保険の選び方
40代女性のがん保険の選び方も基本的には男性と同じですが、罹患するがんの種類が女性特有なものが多い点を考えておく必要があります。
特に罹患率が高い乳がんを患った場合、入院治療以外にも抗がん剤やホルモン治療、リハビリなど通院による治療が長期間にわたって続き、治療費もトータルで高額になることが予想できます。
それらを考慮すると、女性向けのがん保険では
- 診断給付金
- 入院給付金
- 手術給付金
- 通院給付金
などの組み合わせで選ぶと良いでしょう。
また、女性特有のがんに特化したがん保険もありますので、すでに医療保険に加入している人や女性特有のがんの上乗せを考えている人は、女性向けがん保険を検討してみてはいかがでしょうか。
関連記事:女性向けがん保険って必要?20代〜50代の必要性と選び方を比較
まとめ
がんの罹患率は、年齢が上がるほど高くなる傾向にありますが、医療の進歩もあり治る確率も高くなってきています。
しかし一度がんになると、仕事と治療の両立が難しく、収入減などの影響で経済的なリスクが大きくなります。
また、公的保障のみでは足りなくなることがありますので、できるかぎりがん保険への加入を検討するのがおすすめです。
また、40代男性・40代女性とでは「罹患しやすいがんの種類」も異なります。
がん保険選びにおいて「どういった保障内容が自分にピッタリなのか」わからない場合は、一度ファイナンシャルプランナーなど保険をよく知るプロに相談してみるのがおすすめです。
関連記事:40代が知っておくべきがん保険の基礎知識







.jpg?w=300&h=300)




