個人年金保険料控除とは?控除を受けるための条件や注意点を解説
生命保険料控除という制度をご存じでしょうか。生命保険料控除とは生命保険に支払った保険料を所得税や住民税の負担軽減に活用できる制度です。
生命保険料控除は保険の種類に応じ3種類ありますが、この記事では老後の生活資金を備えるための個人年金保険で使える「個人年金保険料控除」を取り上げます。個人年金保険料控除を受けるための条件や注意点、また実際にいくら税金がお得になるのかなどのシミュレーションとあわせ解説いたします。
この記事のポイント
- 個人年金保険料控除を受けるためには、個人年金保険の契約について個人年金保険料税制適格特約の付加や10年以上の保険料払込期間、年金の受取開始年齢が60歳以降かつ10年以上などの条件を満たす必要がある。
- 個人年金保険料控除の申請は給与所得者なら年末調整、自営業者や副業がある人は確定申告で行う。いずれも保険会社から届く「保険料控除証明書」が必要となる。
- 所得300万円で個人年金保険料が年間で10万円の場合、所得税・住民税あわせて年間6,800円、10年間では68,000円の税負担が軽減されるため長期的に見たときのメリットは大きいといえる。
個人年金保険料控除とは

個人年金保険料控除とは、条件を満たした個人年金保険に払い込んだ保険料を年末調整や確定申告で申告することで、所得税・住民税の負担が軽減される制度です。個人年金保険料控除を受けられる条件は後ほど説明いたします。
保険料控除には個人年金保険料控除と、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除が存在します。一般的に、生命保険(死亡保険)は「一般生命保険料控除」、医療保険やがん保険などは「介護医療保険料控除」に該当します。
関連記事:生命保険料控除でいくら戻る?還付金額の計算方法【会社員・個人事業主・パート】
個人年金保険料控除の方法は「確定申告」か「年末調整」の2種類
個人年金保険料控除を受ける方法は「確定申告」もしくは「年末調整」の2種類です。以下で詳しく解説します。
確定申告の個人年金保険料控除
確定申告とは、個人事業主や副業の所得が20万円以上ある方などが、毎年2月から3月に前年度の所得を税務署に申告して支払う所得税を確定させるものです。
この確定申告により、住民税の申告も同時に行われ、申告した所得によって翌年度の住民税額が決定します。
確定申告の際には、収入や経費、各種控除を差し引いた金額が「所得」になりますので、より多くの控除が適用された方が節税につながります。
個人年金保険料控除を受ける場合は、確定申告書の「所得から差し引かれる金額」の「生命保険料控除」に3つの保険料控除の合計金額を記載します。
内訳については別途記載する欄があります。控除の対象金額は各保険会社から送られてくる「保険料控除証明書」に記載してある項目を転記するだけですので、難しい計算等は必要ありません。
※参考:国税庁「確定申告特集」
関連記事:確定申告での生命保険料控除の申告方法とは?生命保険料控除証明書の見方や書類の添付方法などを解説
年末調整の個人年金保険料控除
年末調整は給与所得者が年末に会社から、「給与所得者の保険料控除申告書」が配布されますので、そこに生命保険料控除や個人年金保険料控除の対象となる保険料を記載します。
必要な情報は保険会社から送付される「生命保険料控除証明書」に記載されていますので、そのまま転記しましょう。
関連記事:【2025年】年末調整で生命保険料控除を申告し忘れたらどうなる?その対処法を紹介
個人年金保険料控除を受けるための条件
個人年金保険料控除を受けるためには、個人年金保険料税制適格特約をセットする必要があります。この特約をセットするためには、下記の条件を満たす必要があります。
- 年金受取人が被保険者と同一
- 年金受取者が契約者もしくは配偶者
- 保険料払込期間が10年以上
- 確定年金や有期年金の場合は、受取開始が60歳以降かつ10年以上
個人年金保険料控除の対象となる個人年金かどうかは都度その商品を見て確認することになります。
なお、運用実績によって受け取れる年金額が変動する「変額個人年金保険」については、個人年金保険料控除ではなく、一般生命保険料控除の対象です。
個人年金保険料税制適格特約を付加するときの注意点
個人年金保険料税制適格特約を付加した場合、次のような点に気をつける必要があります。
- 個人年金保険料税制適格特約を付加した場合、特約の付加条件を満たさない契約内容への変更はできない
- 個人年金保険料税制適格特約だけを解約できない
- 基本年金年額の減額などに伴う返戻金がある場合でも支払いはされず、所定の利息をつけて積み立てられ、年金開始日に増額年金の買い増しに充てられる
特約を付加する場合は、付加した時の注意点も確認しましょう。
個人年金保険料控除でいくら税負担が軽減される?シミュレーションで検証
生命保険料控除には2011年12月31日以前に結んだ契約を対象とする「旧制度」と、2012年1月1日以降に結んだ契約を対象とする「新制度」があります。
新制度における個人年金保険料控除額は、以下のように計算できます。
所得税 | 住民税 | ||
|---|---|---|---|
年間払込保険料額 | 控除額 | 年間払込保険料額 | 控除額 |
20,000円以下 | 払込保険料の全額 | 12,000円以下 | 払込保険料の全額 |
20,000円超40,000円以下 | 払込保険料×1/2+10,000円 | 12,000円超32,000円以下 | 払込保険料×1/2+6,000円 |
40,000円超80,000円以下 | 払込保険料×1/4+20,000円 | 32,000円超56,000円以下 | 払込保険料×1/4+14,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 | 56,000円超 | 一律28,000円 |
生命保険料控除を最大限に活用するためには、毎月8万円を超える保険料を支払う必要があります。
つまり、毎月約7,000円の保険料を払い込めば、生命保険料控除の恩恵を最大限受けられ、所得税・住民税の負担も軽減できるということになります。
所得300万円の場合は個人年金保険料控除でいくら税負担が軽減される?
課税所得が300万円、支払い保険料は年間10万円のケースで計算してみましょう。
課税所得とは、収入から社会保険料や給与所得控除などの各種控除等を差し引いた金額です。課税所得が300万円の場合、所得税の税率は10%、住民税は所得に関係なく10%です。
1年間の保険料が10万円の場合は、控除額は所得税は40,000円、住民税は28,000円です。
それぞれの控除額に対してかけられる税金が軽減されますので、所得税は4,000円(40,000円×10%)、住民税は2,800円(28,000円×10%)軽減されるということです。
個人年金保険料控除による所得税・住民税の軽減額早見表
下記は、個人年金保険料控除の新制度(所得税4万円、住民税2.8万円)の上限額での、課税所得額別の税金の軽減額の早見表です。
課税所得 | 税率 | 所得税の軽減額 | 住民税(10%)の軽減額 |
|---|---|---|---|
195万円以下 | 5% | 2,000円 | 2,800円 |
195万円超 330万円未満 | 10% | 4,000円 | |
330万円超 695万円未満 | 20% | 8,000円 | |
695万円超 900万円未満 | 23% | 9,200円 | |
900万円超 1,800万円未満 | 33% | 13,200円 | |
1,800万円超 4,000万円未満 | 40% | 16,000円 | |
4,000万円超 | 45% | 18,000円 |
保険料控除以外の個人年金保険のメリットとは

個人年金保険とは、公的年金とは別に個人が保険会社と契約して加入する保険です。
契約時に定めた一定期間受け取れるタイプ・一生涯受け取れるタイプなどがあり、将来設計や保険料に応じて選択します。
年金2,000万円問題で多く取り上げられたように、公的年金だけでは老後の生活を賄うことは難しいと言われていますので、個人年金などに加入して老後に備えることを多くの方が検討しています。
個人年金保険に加入すべきかどうか、加入する場合は保険料や保険金額をどう設定すべきかについては、ファイナンシャルプランナーなどに相談してみるのがおすすめです。
関連記事:個人年金保険の選び方・見直し方を徹底解説!注意点や保険料の節約方法とは?
まとめ
個人年金保険料控除を活用すれば、所得税や住民税の負担を軽減しつつ、老後に向けた資産形成ができます。ただし、個人年金保険は契約してから短期間で解約すると元本割れするリスクがあります。また、将来年金を受け取る際に物価が上昇(インフレ)していると、保険金の価値が実質的に目減りしてしまうかもしれません。
「税負担を軽減できる」というメリットだけではなく、これらのデメリットやライフプランを考慮した上で、加入を検討しましょう。
個人年金保険に加入すべきかどうか、また加入する場合の保障内容などを知りたい場合は、コのほけん!の無料保険相談もぜひご利用ください。
さらに、個人年金保険の保険料控除についてより詳しく知りたい場合は、【しっかり保険、ちゃんと節約。】個人年金保険の保険料控除でいくら戻ってくる?シミュレーションを用いた計算方法と注意点を解説, 個人年金保険に税金はかかる?受け取り方によって変わる税金を計算シミュレーションで紹介も参考になります。


.jpg?w=300&h=300)
.jpg?w=300&h=300)


.jpg?w=300&h=300)
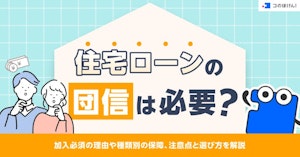


.jpg?w=300&h=300)
.jpg?w=300&h=300)
