祖父母から孫への教育資金援助と学資保険の活用について
祖父母などが孫に対して教育資金を援助する場合、教育資金一括贈与の非課税制度や学資保険の活用などさまざまな方法が考えられます。
しかしそれぞれの方法における仕組みや注意点をよく理解したうえで利用しないと、後になって思いがけない税金の負担が発生する可能性があるため注意が必要です。
そこで今回は、教育資金の援助をする場合に考えられる手段や仕組み、注意点などについて解説します。
教育資金の一括贈与時の非課税制度とは
教育資金の一括贈与時の非課税制度とは、教育資金としてお金を一括で贈与した場合、最高1,500万円まで贈与税が非課税となる制度です。祖父母の財産を教育資金として孫に贈与することで、財産を圧縮して相続税の負担を軽減できます。
具体的には、祖父母のような直系尊属から以下のような贈与を受けた場合を対象としています。
- 信託受益権を取得した場合
- 書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合
- 書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合(以下「教育資金口座の開設等」といいます。)
また、贈与をしてもらう側である受贈者は、30歳未満の方が対象です。
本来、1年間で110万円以上の贈与を受けた場合は贈与税を支払わなければなりません。
仮に、非課税制度を使わずに1,500万円を贈与されると、366〜450万円程度の贈与税がかかってしまいます。教育資金の一括贈与の非課税制度を利用することで、一括で資金を贈与しても贈与税を納める必要がなくなるため、贈与税を負担せずに資金提供ができるのです。
一括贈与非課税制度の利用可能期間と教育資金の定義
教育資金の一括非課税制度が利用できる期間は、平成25年4月1日から令和3年3月31日までの間です。
贈与された資金は、原則として教育資金にしか充てられません。対象となる教育資金は、以下の2種類に分かれます。
- 学校等に直接支払われる金銭
- 学校等以外の者に対して直接支払われる金銭
それぞれについて確認していきましょう。
学校等に直接支払われる金銭
以下のように、小学校や中学校などの学校に支払われる入学金や授業料が対象です。
①入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費又は入学(園)試験の検定料など
②学用品の購入費、修学旅行費や学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など
※学校等とは学校教育法で定められた幼稚園、小・中学校、高等学校、大学(院)、専修学校及び各種学校、一定の外国の教育施設、認定こども園又は保育所など
学校等以外の者に対して直接支払われる金銭
次のような金銭で教育を受けるために支払われるものとして、社会通念上相当と認められるものも教育資金の対象となります。
<イ 役務提供又は指導を行う者(学習塾や水泳教室など)に直接支払われるもの>
③教育(学習塾、そろばんなど)に関する役務の提供の対価や施設の使用料など
④スポーツ(水泳、野球など)又は文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画など)その他教養の向上のための活動に係る指導への対価など
⑤、③の役務の提供又は④の指導で使用する物品の購入に要する金銭<ロ イ以外(物品の販売店など)に支払われるもの>
⑥、②に充てるための金銭であって、学校等が必要と認めたもの
⑦、通学定期券代、留学のための渡航費などの交通費
※令和元年7月1日以後に支払われる上記③~⑤の金銭で、受贈者が23 歳に達した日の翌日以後に支払われるものについては、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するための費用に限ります。
社会通念上で相当と認められないものには、例えば、以下のような費用が挙げられます。
- 酒やタバコなどの購入費用
- 麻雀やカラオケ、旅行、遊園地の入園料などの娯楽費用
また、学校等以外の者に対して直接支払われる金銭で非課税となるのは、500万円までとなるため注意しましょう。
教育資金の一括贈与非課税制度の適用条件と手続き方法
教育資金の一括贈与非課税制度を利用するには、金融機関を通じて専用の口座を開いて資金を管理しなければなりません。「教育資金だよ」と言って孫に渡すだけでは、非課税とはならない点に注意しましょう。
口座を開設できる金融機関は、以下の通りです。
- 銀行
- 信託銀行
- 証券会社
また、保有できる口座は受贈者1人につき1口座のみしか開設できません。
口座を開いたら、金融機関に教育資金非課税申告書の提出が必要です。教育資金非課税申告書は、金融機関を通じて受贈者の納税地を管轄する税務署に提出されます。
また、教育資金口座から教育資金を支払った場合は、支払いに充てた領収証など支払いの事実を証明する書類を提出しなければなりません。書類の提出期限は以下の通りです。
〜
(1)教育資金を支払った後にその実際に支払った金額を口座から払い出す方法を選択した場合:領収書等に記載等がされた支払年月日から1年を経過する日
(2)(1)以外の方法を選択した場合:領収書等に記載等がされた支払年月日の属する年の翌年3月15日
※上記(1)又は(2)の教育資金口座の払出方法の選択は、受贈者が教育資金口座の開設等の時に行う
このように、非課税制度を利用するには、口座を開くだけでなく支払いに充てた領収書なども提出しなければならないため、管理に手間がかかる点に注意が必要です。
一括贈与の非課税制度を利用しても税金がかかる場合がある
教育資金の贈与にかかる契約が終了したり、贈与期間中に贈与者が亡くなったりした場合は、贈与税や相続税の対象となる可能性があります。
贈与税の対象となる場合
以下のいずれかに当てはまると、教育資金の贈与にかかる契約が終了となり、贈与税が発生する可能性があるため注意しましょう。
- 受贈者が30歳に達した場合(学校等に在学または教育訓練校に在学しているかつ金融機関に届けている場合は除く)
- 30歳以下の受贈者がその年中のいずれかの日において学校等に在学した日又は教育訓練を受けた日があることを、取扱金融機関の営業所等に届け出なかったこと場合
- 受贈者が40歳に達した場合
- 受贈者が死亡した場合
- 口座の残高がゼロになり、口座に係る契約を終了させる合意があった場合
上記のうち、4を除く理由で契約が終了し残額が存在する場合は、契約が終了する日が属する年の贈与税の課税対象となります。
また、教育費以外で資金を使った場合は、契約が終了したときに贈与税の支払いが必要です。資金を使った年に贈与税を支払うのではなく、最後にまとめて課税される点に注意しましょう。
相続税の対象となる場合
贈与者の死亡から3年以内かつ平成31年4月1日以後に、教育資金を追加で拠出(非課税拠出)した場合に、所定の計算式で求められた管理残高に対して相続税が課税されます。
管理残額の計算式は、以下の通りです。
B 贈与者の死亡前3年前かつ平成31年4月1日以後に追加拠出した金額
C 口座開設時に拠出した金額
仮に、Aが1,200万円、Bが1,000万円、Cが500万円である場合、管理残高は800万円となり相続税の課税対象となります。
ただし受贈者が贈与者の死亡日に以下の状態であった場合は、相続等によって取得したとみなされず、管理残高に対して相続税が課せられません。
- 23歳未満
- 学校等に在学している
- 教育訓練給付金の支払い対象となる教育訓練を受けている
例えば、受贈者が21歳で大学に在籍しているようなケースでは、相続税の課税対象外となります。反対に受贈者が社会人として独立しており、教育資金口座にお金が残っている場合は、受贈者の死亡によって相続税が課税される可能性があります。
教育資金の一括贈与非課税制度はどんな人におすすめ?
教育資金の一括贈与非課税制度の利用がおすすめな人は、以下の通りです。
短期間で相続税対策をしたい人
例えば、重い病気にかかっており余命が短い場合は、教育資金の一括贈与非課税制度を利用することで、短期間で最大1,500万円を相続税の課税対象から除外できます。
資金を贈与した場合、年間で110万円までなら贈与税はかかりません。しかし余命が短い場合、年間110万円ずつの贈与だけでは、相続税の対象となる財産の圧縮が進まず対策が不十分となる可能性があります。
そもそも教育資金の贈与は、一括贈与の非課税制度を利用しなくても非課税ですが、教育資金が必要になったタイミングで贈与しなければなりません。大学への進学資金のような将来に必要になる資金をあらかじめ贈与すると、贈与税の対象となってしまうのです。
そこで、教育資金の一括贈与非課税制度を利用することで、教育資金の必要なタイミングでなくともまとまったお金を非課税で贈与でき、相続税の課税対象財産を短期間で圧縮できます。
反対に、相続税の対策をする必要がない人や、教育資金を必要なタイミングで贈与する予定の人は、教育資金の一括贈与非課税制度の必要性は、低いといえるでしょう。
教育資金を贈与しても自分たちの生活費が困らないような人
所有している金融資産に余裕があり、教育資金を一括で贈与しても生活に支障がない場合は、教育資金の一括贈与非課税制度の利用がおすすめです。
ただし、老後の生活は介護費用や医療費などで想定以上にお金がかかる場合があります。一度教育資金として贈与したお金は、贈与者に返却されないため、金銭面で不安が生じないか入念に検討しましょう。
暦年贈与をする際の注意点
暦年贈与とは、暦年(1月1日〜12月31日まで)ごとにお金を贈与し、贈与者1人につき110万円まで非課税となる制度のことです。
長年にわたって教育資金を贈与できる場合は、口座の管理が大変な教育資金の一括贈与非課税制度よりも暦年贈与の方が良い場合があります。また、教育資金の一括贈与非課税制度を利用していても、暦年贈与を利用することが可能です。
ただし、1年で110万円ずつ贈与したとしても、「定期金給付契約に基づく権利の贈与」に該当すると贈与税が発生する可能性があるため注意が必要です。
例えば、毎年110万円を10年間にわたって1,100万円渡した場合、初めから1,100万円を贈与するつもりだったと税務署に判断されると贈与税の対象となってしまいます。
定期金給付契約に基づく権利の贈与への該当を防ぐ方法は、以下の3つの方法が考えられます。
- 贈与契約書を毎年作成する
- 贈与する金額を変える
- 贈与する時期をずらす
このような対策を行い、毎年単発の贈与が発生しているとみなされると、定期金給付契約に基づく権利の贈与にあたらなくなり贈与税の課税を避けられると考えられます。
相続税にも注意が必要
暦年贈与において、贈与者が死亡する前の3年間で贈与した金額は、相続税の対象となる場合があります。
また、資金を贈与する時に、孫や子供の名義の口座に、お金を入金するだけでは贈与にならず自分の財産とみなされる可能性があります。
自分の財産とみなされると、亡くなった場合に相続税の課税対象となるため、贈与をする場合は、贈与する人の口座から贈与される人の口座に送金をして贈与した事実が残るようにしましょう。
学資保険を活用した暦年贈与
暦年贈与を行う際に、お金を直接渡すのではなく学資保険に加入する方法があります。学資保険に加入することで、手元にある金額以上の教育資金の援助が可能です。
ケース1 契約者を祖父母、保険金の受取人が孫にして学資保険に加入する
このケースでは、契約者と受取人が別になるため、保険金やお祝い金は贈与税の対象となります。
仮に、大学に入学した時から5年間にわたって100万円の保険金が受け取れる学資保険に加入したとすると、保険金額が110万円以下のため贈与税負担することなく教育資金を援助できます。
ケース2 祖父母が子供(親)に贈与したお金で学資保険に加入する
祖父母が自分自身の子供(親)に資金を贈与し、契約者と受取人を親にして学資保険に加入する方法です。
この場合、最大で年間110万円を学資保険の保険料に充てられます。そのため、ケース1よりも学資保険の保険金を高く設定でき、援助できる教育資金の額も高くなります。
仮に、年払保険料が104万円で払込期間が10年間、返戻率※が105.7%の学資保険に加入すると約1100万円の教育資金を贈与することが可能です。
ただし、保険料分を贈与する祖父母は、定期金給付契約に基づく権利の贈与とみなされないように注意しながら資金提供を行いましょう。
※返戻率とは支払った保険料の総額に対する受け取った保険金総額の割合
まとめ
教育資金の一括贈与非課税制度は、祖父母のような直系尊属が30歳未満の孫などに、教育資金を提供した場合、最大1,500万円まで贈与税が非課税となる制度です。
ただし教育資金の一括贈与非課税制度は、金融機関で専用の口座を開いた上で管理をしていかなければなりません。また場合によっては贈与税や相続税の対象となる可能性もあるため運用には利用には注意しましょう。
また、教育資金の援助方法は、一括贈与非課税制度だけではなく、暦年贈与を活用する方法も考えられます。さらに学資保険も活用することで、手元にある資金以上の教育資金を援助できる場合があります。
もし、自分に有効な教育資金援助方法が合っているか分からない場合は、保険の専門会やファイナンシャルプランナーといった専門家の意見を参考にするのも一つの方法です。非課税制度や学資保険の仕組みを理解したうえで、最適な手段を選べるでしょう。
.jpg)
.jpg)
.jpg)

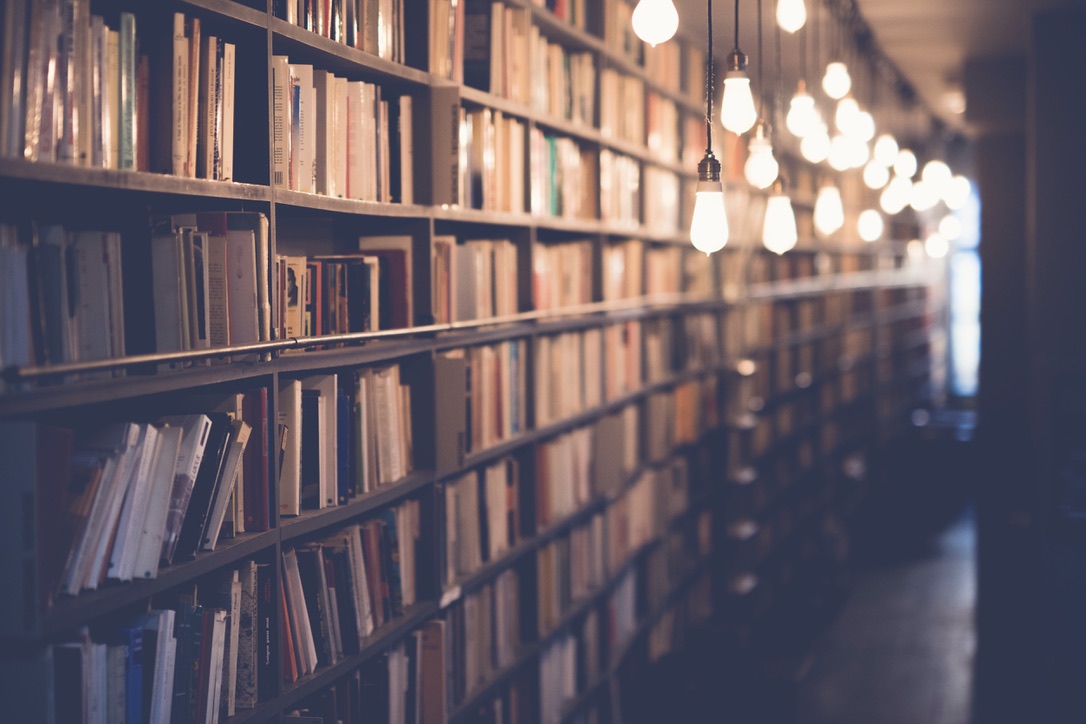
.jpg)
![女性特有の病気に備えたい方におすすめ!オリックス生命の医療保険CURE Lady Next[キュア・レディ・ネクスト]人気の理由を大調査](https://images.microcms-assets.io/assets/f84aa30f91624818a0311521de70d1bb/06f46e9d2e1c47f1a4f7b229c50ad686/AdobeStock_334906465%20(1).jpg)
.jpg)
.jpg)


