寡婦控除(かふこうじょ)とは?受給要件や申告方法、ひとり親控除との違いをわかりやすく解説
家族のかたちが多様になる中、税のしくみも変化しています。
配偶者との死別や離婚を経た女性が要件を満たせば利用できる寡婦控除について、未婚の方も含め、子どもを育てるシングルマザー・シングルファザーの方が利用できるひとり親控除や扶養控除と比較しながらわかりやすく解説します。
この記事のポイント
- 寡婦控除は配偶者と離別・死別後に再婚していない女性が対象となる。所得や扶養状況により所得税・住民税合わせて約4万円の税負担が軽減されることもある。
- ひとり親控除は男女とも対象となり寡婦控除より控除額も大きい。寡婦控除・ひとり親控除の両制度の要件を満たす場合は、ひとり親控除を適用することが一般的である。
- 寡婦控除は婚姻歴のある女性のみ利用できる制度だが、扶養控除は性別・婚姻歴を問わず利用できる。
そもそも寡婦とは?
.jpg?w=930&h=620)
寡婦、というのは聞き慣れない言葉ですね。「寡婦」とは、夫と死別または離縁した後、再婚せず、ひとりでいる女性のことを指しています。
同様に配偶者と死別または離縁した後ひとりでいる男性のことを「寡夫」と言います。いずれも「かふ」と読みますが、「寡婦」と書いて「やもめ」と読む場合もあります。
寡婦控除とは?
寡婦控除は、寡婦となった方のうち、一定の要件を満たした方が受けられる所得控除です。所得控除はいわば、個々の事情に応じて税金負担を減らすことができるしくみです。
寡婦控除によって減らせる税金は、所得税と住民税です。所得税と住民税の税金額は、基本的に課税所得金額に一定の税率をかけ算することで算出できます。所得控除は一定の税率をかけ算する前に、課税所得から差し引くことができますから、所得控除の分だけ課税所得を減らし、その結果として税金額を減らすことができます。
寡婦控除により差し引くことができる金額は、所得税で27万円、住民税では26万円です。いくら税金額を減らせるかは所得によっても異なりますが、寡婦控除適用により所得の低い方でも所得税・住民税あわせて、毎年4万円程度税金負担を減らせることが見込まれます。
寡婦控除の対象者
寡婦控除の対象となるかどうかは、原則としてその年の12月31日時点の現況で判断されます。寡婦控除の対象となるのは女性で、かつ以下のような方です。
- 夫と離婚したあと婚姻をしておらず、かつ扶養親族がいる方
- 夫と死別(一定の生死不明を含む)したあと婚姻をしていない方
- 「ひとり親」に該当しない方
- 納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいない方
なお、夫は「民法上の婚姻関係にあった夫」を指しており、事実婚や内縁の夫は含まれません。
「ひとり親」とは、子どもを育てる方のうち現在婚姻していない方を指しています。具体的には離婚または死別(一定の生死不明を含む)のあと結婚せずおひとりで子どもを育てている方や、未婚で子どもを育てている方が対象となっています。ひとり親にあてはまる場合、寡婦控除は利用できません。しかしその場合は同じく所得控除の1つである「ひとり親控除」を利用できます。
ひとり親控除を受けるにあたっては、以下の3つの要件すべてを満たす必要があります。
- 生計を一にする子どもがいること
- 合計所得金額が500万円以下であること
- 納税者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいない方
要件の一つとなっている子どもについては、未成年者である必要はないものの、その年分の総所得金額等が48万円以下で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族になっていない人に限られています。また、「生計を一にする」とは、必ずしも同居している必要はありません。例えば、大学に通学するために下宿しているなどの理由で別居している場合にも、休みの時には帰省しており、常に仕送りが行われているなどの場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
寡婦控除の受給要件
寡婦控除の利用には、その他の細かい要件もあります。
- 合計所得金額が500万円以下であること
- (夫と離婚された方)その年の12月31日の現況において、以下の要件をすべて満たす扶養親族がいること
- 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)、都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)または市町村長から養護を委託された老人であること
- 納税者と生計を一にしていること。
- その年の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみの方は103万円以下)であること
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていない、または白色申告者の事業専従者でないこと
合計所得金額とは、配当所得や公的年金等の雑所得、給与所得や不動産所得などの総合所得に退職所得などの分離所得を加えた金額です。純損失の繰越控除や雑損失の繰越控除等を適用する前の金額となります。夫と死別された方は遺族年金を受け取っている方もいらっしゃることでしょう。遺族年金は非課税です。したがって遺族年金から受け取った金額は合計所得金額には含まれません。
なお、夫が年の途中でなくなった時には、なくなった時点での夫の合計所得金額が48万円以下など一定の要件を満たせば、配偶者控除もあわせて適用を受けられる可能性があります。
寡婦控除とひとり親控除や扶養控除の違い
寡婦控除はひとり親控除や扶養控除とはどのような違いがあるのでしょうか。それぞれ比較しながら内容を確認していきましょう。
ひとり親控除との違い
ひとり親控除と寡婦控除の違いを表にまとめました。主な違いは以下のとおりです。
ひとり親控除 | 寡婦控除 | |
|---|---|---|
対象 |
|
|
扶養要件 | 生計を一にする子(総所得金額48万円以下) | 【離婚した妻の場合】生計を一にする扶養家族(合計所得金額48万円以下) |
納税者本人の性別 | 男女不問 | 女性のみ |
納税者本人の所得要件 | 合計所得500万円以下 | 合計所得500万円以下 |
控除額 | 所得税35万円、住民税30万円 | 所得税27万円、住民税26万円 |
「No.1171 ひとり親控除|国税庁」「未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し等|総務省」を参照し筆者が表を作成
大きく違うのは、寡婦控除では女性だけが対象となるのに対し、ひとり親控除では要件を満たせば男女ともに対象となることです。
また、寡婦控除はこれまでに婚姻歴がある方が対象となっているのに対し、ひとり親控除では過去の婚姻歴は問われないかたちになっています。ひとり親控除は現在事実婚を含め結婚していないことが要件の1つとなっており、未婚のひとり親の方も要件を満たせば利用できるようになっています。
いずれも納税者ご本人の所得要件は合計所得500万円以下です。給与収入のみの方であれば、年収の目安は870万円未満です。(※基礎控除と社会保険料控除のみ考慮し、社会保険料は年収の15%とした場合)。
控除額はひとり親控除の方が大きく、所得税では8万円の差があります。ひとり親控除と寡婦控除、どちらの要件も満たしている、という場合は控除額の大きいひとり親控除を適用します。
なお、どちらにしても適用できる場合は、前年の合計所得金額が135万円以下(給与のみの場合は給与収入が204万4,000円未満)であれば、個人住民税が非課税となります。
扶養控除との違い
次に寡婦控除と扶養控除の違いについて見ていきましょう。主な違いは以下のとおりです。
扶養控除 | 寡婦控除 | |
|---|---|---|
対象 | 扶養している親族がいる方 |
|
扶養親族の要件 |
| 【離婚した妻の場合】 生計を一にする扶養家族 (合計所得金額48万円以下) |
納税者本人の性別 | 男女不問 | 女性のみ |
納税者本人の所得要件 | なし | 合計所得500万円以下 |
控除 | (一般扶養控除)
(特定扶養控除)
(老人扶養控除)
| 所得税27万円、住民税26万円 |
「No.1180 扶養控除|国税庁」「未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し等|総務省」を参照し筆者が表を作成
寡婦控除は過去に婚姻歴がある女性のみを対象としていますが、扶養控除の対象となる方の範囲は比較的広く、性別や婚姻歴を問わず、生計を一にする親族を扶養している方が利用できます。扶養親族の所得要件はどちらも合計所得金額48万円以下ですが、扶養控除で対象となる親族は16歳以上です。控除額の設定は、寡婦控除はシンプルですが、扶養控除は扶養する親族によって4パターンに分かれています。
扶養控除を利用する際は、控除の対象とする扶養親族ごとに控除額を確認しておきましょう。
寡婦控除の申告方法
寡婦控除の申告方法は2つあります。確定申告で申告する方法と年末調整で申告する方法です。それぞれの方法を詳しくみていきましょう。
確定申告の場合
確定申告で申告をする場合、まずは確定申告書の第一表と第二表を用意しましょう。
まず、第一表「所得から差し引かれる金額」欄の中ほどの「寡婦、ひとり親控除」欄に控除額を記載します。寡婦控除の控除額は前述のとおり所得税と住民税で異なりますが、こちらに記載するのは所得税の所得控除額です。したがって「270,000」と記載します。

国税庁「申告書第一表・第二表【令和4年分以降用】(PDF/600KB)」を参照して筆者作成
第二表も確認しましょう。「本人に関する事項」欄の「寡婦」に○をつけ、下段「死別」「生死不明」「離婚」「未帰還」いずれかあてはまるものにチェックを入れていきましょう。

国税庁「申告書第一表・第二表【令和4年分以降用】(PDF/600KB)」を参照して筆者作成
過去の分の申告を忘れていた場合は更正の請求をすることで、還付を受けることができます。更正の請求で遡れるのは最大で5年間です。なお、もともと税金がかかっていない非課税世帯の方などの場合は、申告しても還付を受けることはできません。
年末調整の場合
会社員など給与収入のみという方は、年末調整の際「扶養控除等(異動)申告書」に記入し、勤務先に提出することで申告を終えることができます。「扶養控除等(異動)申告書」の氏名や住所欄、そのほか必要な項目を埋めていれば、寡婦控除の申告はC欄「障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生」の右側「寡婦」のチェックボックスにチェックを入れるだけで完了します。

国税庁「給与所得者の扶養控除等申告書」を参照して筆者作成
過去の分の申告を忘れ控除を受けていない場合、還付申告をすることで、還付を受けることができます。還付申告は所轄の税務署で行うことができます。お近くの税務署を調べて確定申告書を提出しましょう。
なお、寡婦控除は2020年の改正により、2019年以前と2020年以降で適用の要件が違っています。2019年以前分であれば、子どもや扶養親族がいる方は合計所得金額500万円を超える場合も寡婦控除を適用できる可能性があります。
まとめ
死別や離縁など寡婦となる理由はさまざまですし、そのお気持ちは計り知れませんが、いずれにしても寡婦となった後に生活設計を大きく見直さなければいけなくなったという方は少なくないことでしょう。寡婦控除を利用することで、納税額を減らし日々の経済的な負担を減らすことが可能となります。
とはいえ残念ながら暮らし向きを大きく改善する効果があるものではありません。納税額が減って手元に残せるお金を増やせたら、今のあなたと未来のあなたが少し元気になれるお金の使い方を考えてみてください。


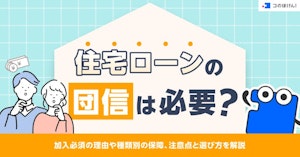






.jpg?w=300&h=300)
.jpg?w=300&h=300)
