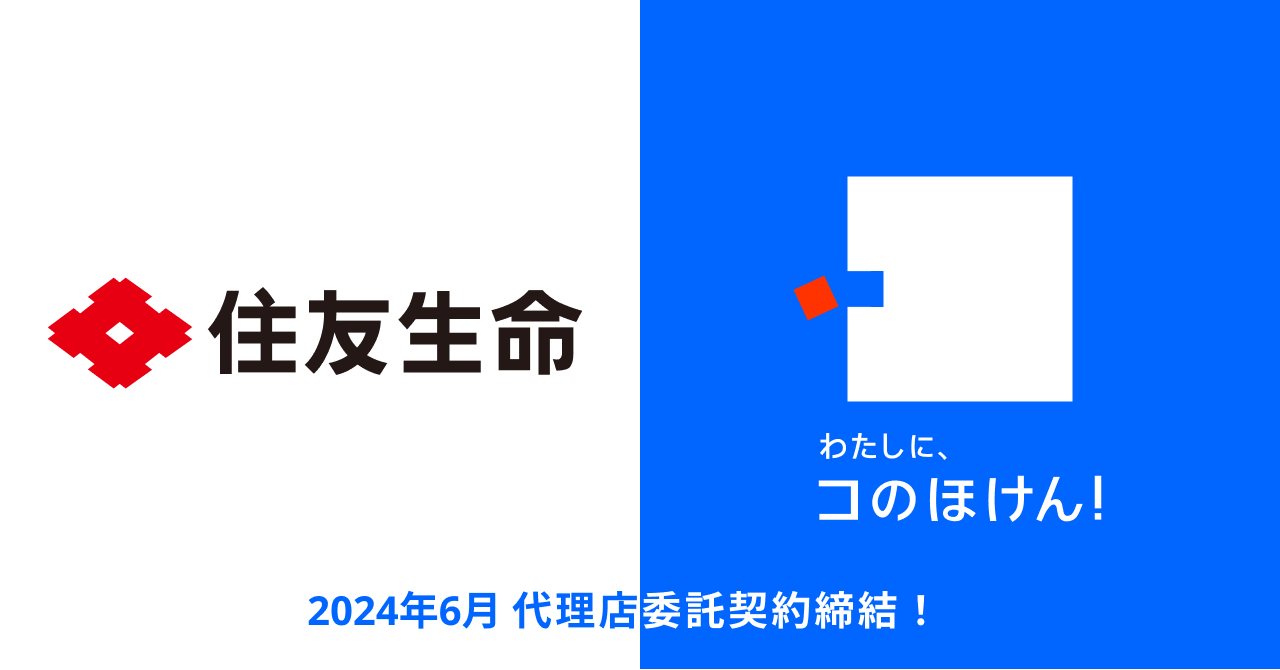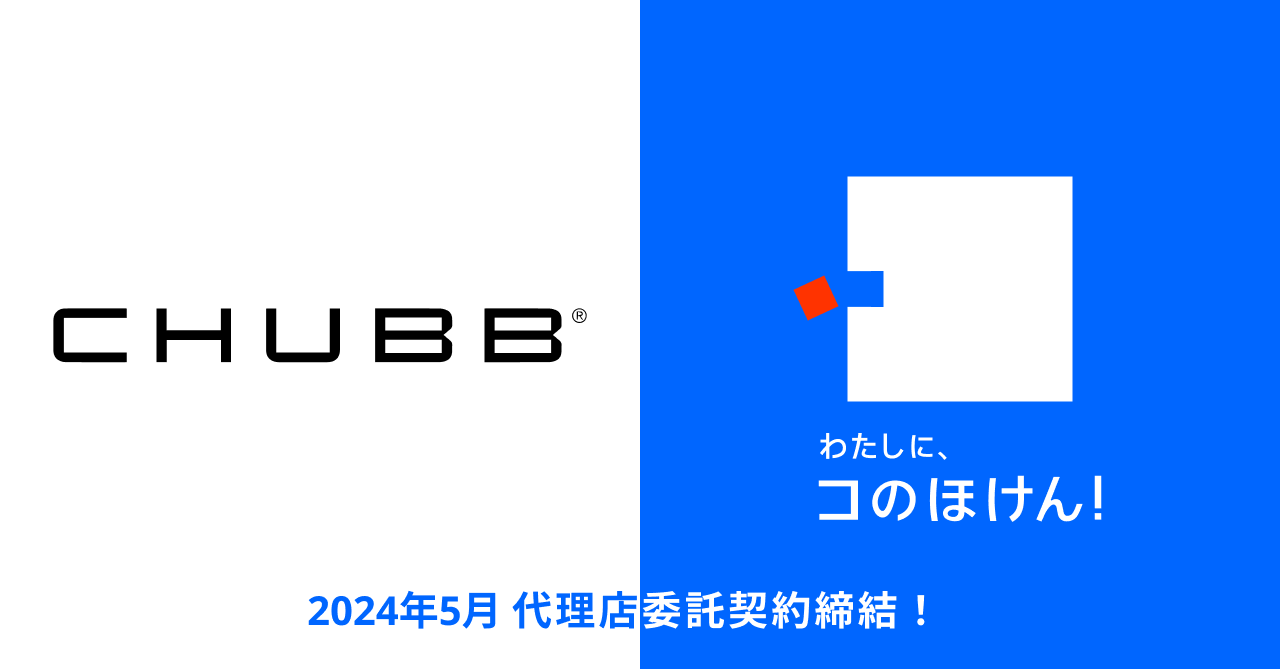Sasuke Financial Lab株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役:松井清隆、以下「当社)は、White Paper「2023年度改訂版 生命保険が直面する多様な問題とInsurTech」を公開したことをお知らせ致します。
生命保険が直面する多様な問題とInsurTech
▼PDFはこちら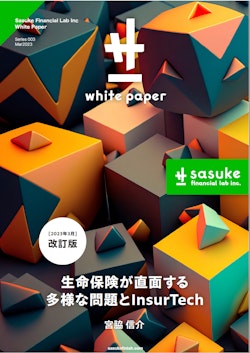
■まとめ
- コロナ禍は終局に向かいつつある模様だが、2020 年春から 3年間におよび続いたことによる、消費者の行動や政策対応へ与えた影響は大きい。対面営業が制約される中、「インターネット生保」は順調に新規の契約を伸ばしてきた。
- しかしながら、生命保険全般が伸び悩む傾向は、コロナ禍の影響だけではなく複合的な要因を背景としていると考えられる。インターネット・リテラシーの制約もあり、インターネット販売の強化だけでは即効性のある特効薬とはならない公算。
- コロナ禍中において営業職員がタブレット端末を携行することが一般化した。これは本来的な意味でのDX( デジタル技術を用いたビジネスの改革) を押し進めるための基盤と なる可能性がある。
- 「InsurTech = 保険× テクノロジー」の多様な原義に立ち戻れば、インターネットを通じた保険販売は InsurTech の一つの限定的な例でしかなく、InsurTech は様々な解を生み出す可能性を有している。
■執筆者:取締役 宮脇 信介(みやわき のぶすけ)
2017年からSasuke Financial Lab株式会社の取締役を務める。東京大学経済学部を卒業後、日本興業銀行等で金融市場分析や株式・債券の運用業務に従事。米国カリフォルニア大学バークレー校でMBAを取得後、ブラックロック等外資系運用会社に勤務し、債券運用ならびに債券投資プロダクト開発等を行う。尚、2014年に日本フェンシング協会常務理事に就任、2017年より専務理事を務める。協会運営の透明化・ガバナンス強化、企業と連携した副業兼業プロジェクトによる外部人材の活用など、様々な経営課題の解決に取り組む。
〈主な資格〉
CFA協会認定証券アナリスト(CFA)
日本証券アナリスト協会検定会員(CMA)
≪引用・転載時のクレジット表記のお願い≫
本ホワイトペーパーやリリースの引用・転載時には、必ず当社クレジット「Sasuke Financial Lab株式会社 ( https://sasukefinlab.com/ )」を明記いただけますようお願い申し上げます。
以下、抜粋。
(1)好調なインターネット生保の保険販売
コロナ禍は、伝統的な大手生保が強みとする対面営業に大きな足枷(あしかせ)となったが、(中略)(インターネット生保の)新契約件数の伸びは、業界全体と比較して、明確に堅調に推移してきた。
(2)ここ数年伸び悩む生保契約
2017 年頃までは、(名目)可処分所得の低下に合わせて保険料の支払いもほぼ一定の関係を保ちながら低下してきた。(中略)2017年頃からは2017 年頃から2020 年にかけて可処分所得は増加したが、保険料に関する支払いは、過去の関係性を失い、概ね横ばいのまま停滞して推移した。更にコロナ禍の影響を受けた2022 年にかけて、この5 年間程度は、家計は収入から税金(直接税)・社会保険料等を差し引いて残ったお金(可処分所得)が
増える傾向にあったにも関わらず、そこから追加的な保険料を払おうとせずに、原則として預貯金に回してきたと読める。(中略)2019年の消費税引き上げや2020 年のコロナ禍の深刻化など、家計の消費・資金配分行動をより保守的とする要因が重なり、家計の余剰資金が預貯金に流れた側面があったと考えられる。
(3)「贅沢品」としての生命保険に「構造的変化」も
統計的にみると、生命保険には「贅沢品」としての性格がある。(中略)個別の世帯の行動において、世帯主が高齢化するにつれて(可処分所得の増加を背景に)保険契約を積み増すことを一つの要因としていると考えられる。
ところが、この10 年間の変化としては、年齢が上になればなるほど保険料支払に対して抑制的になってきている、いわば「保険離れ」が進んでいるという変化が見て取れる。
(4)もうひとつの有力な仮説:公的な社会保険料の「クラウディングアウト」
ここでもうひとつの可能性について考えてみたい。
それは、近年増加傾向にある国など公的な「社会保険料」の支払いである。この項目には、「公的年金保険料」、「健康保険料」、さらに2000 年代に入り導入された「介護保険」などの負担が入る。このような家計負担は、2000 年代央をボトムとして、特に2010年頃から明確な増加傾向にあり、生命保険や個人保険等の民業(含む簡易保険)を圧迫しているとの見方である。
この様な公的「社会保険料」と民業の「保険料支払」をひとつの固まりと捉えてみてみると、確かに変動幅は相対的には限定的であり、「社会保険料」負担の増加が生命保険等の支払い水準をある程度圧迫している可能性がある。すなわち、公的保険による民業の保険に対する「クラウディングアウト」が、限定的ながらおきていると解釈することが出来ると思われる。
(5)InsurTech は生命保険の切り札となるのかという問いのヒントとして
これまでの議論で見えてきたのは、コロナ禍による影響は短期的なものであり、むしろ増加した収入が「非経常的」というここ数年間の影響や、さらに公的「社会保険料」支払い増の影響もうけた「保険離れ」という長期的、構造的な経営課題である。
これに対して、インターネットを通じた保険販売は、一定の効果は見込まれるものの、インターネットを経由した情報収集や保険加入が限定的な状況もあり、これら全ての問題に対する決定的な特効薬として不十分なものとならざるを得ないであろう。
(中略)「InsurTech = 保険× テクノロジー」の多様な原義に立ち戻れば、InsurTech は様々な解を生み出す可能性を有している。
InsurTech は唱えれば一瞬にしてあらゆる問題を解決する「魔法の呪文」ではないが、向き合っている問題に即して適切・丁寧に建付けを行うことによって、生保ビジネスのあらゆる分野について、イノベーションを通じた課題解決を提供することが可能な「現実的な取り組みの手法」に与えられた総称であると考えている。