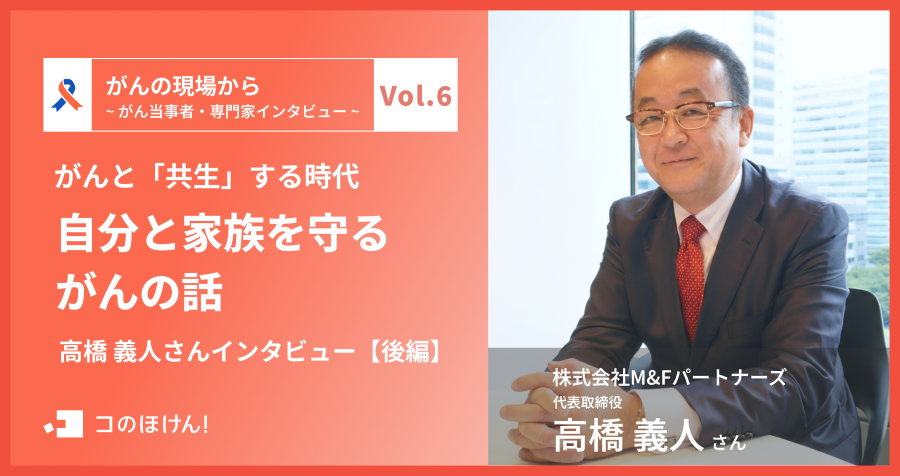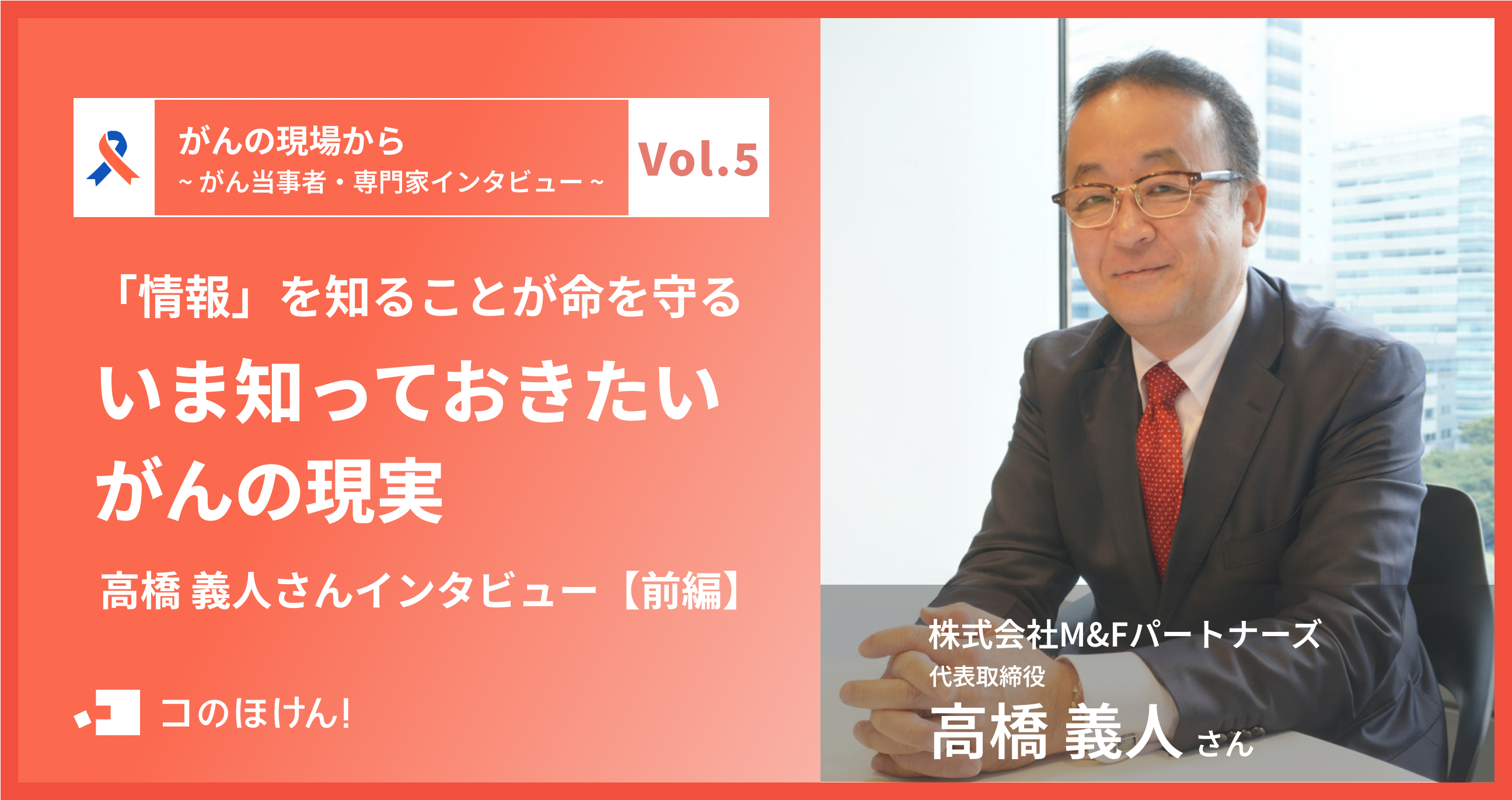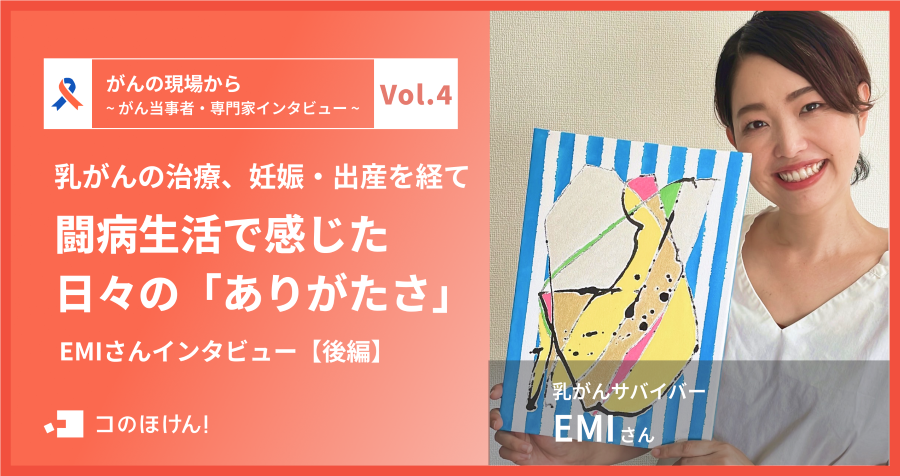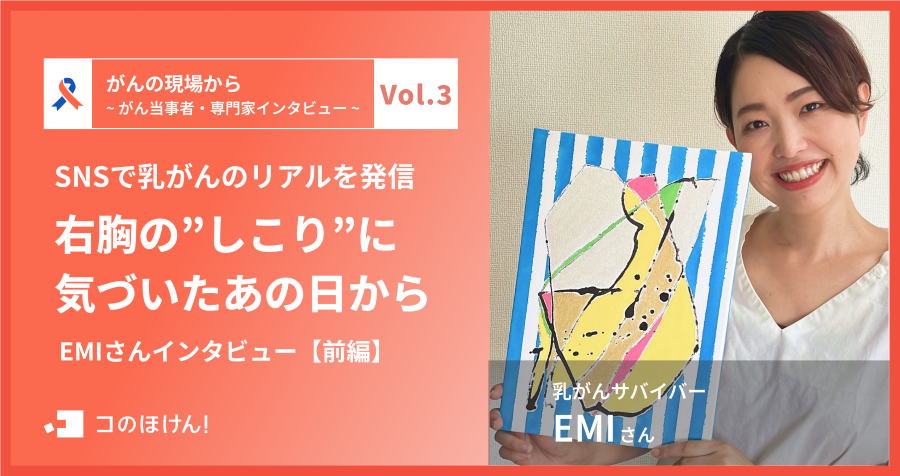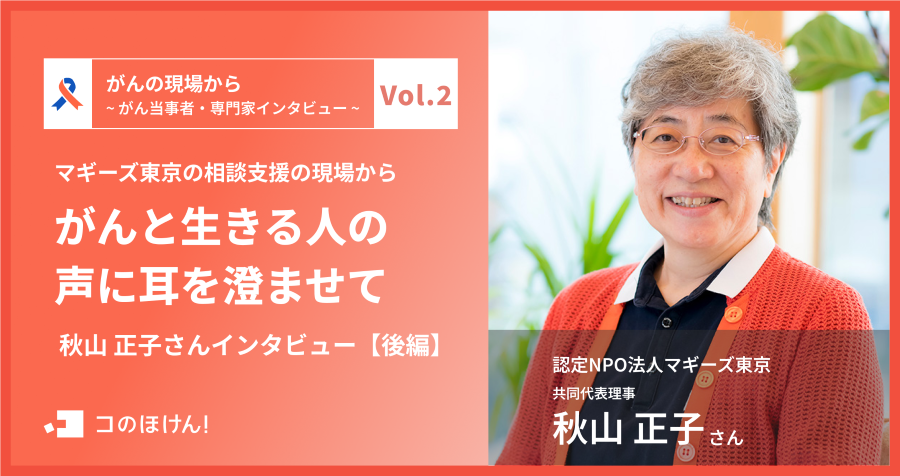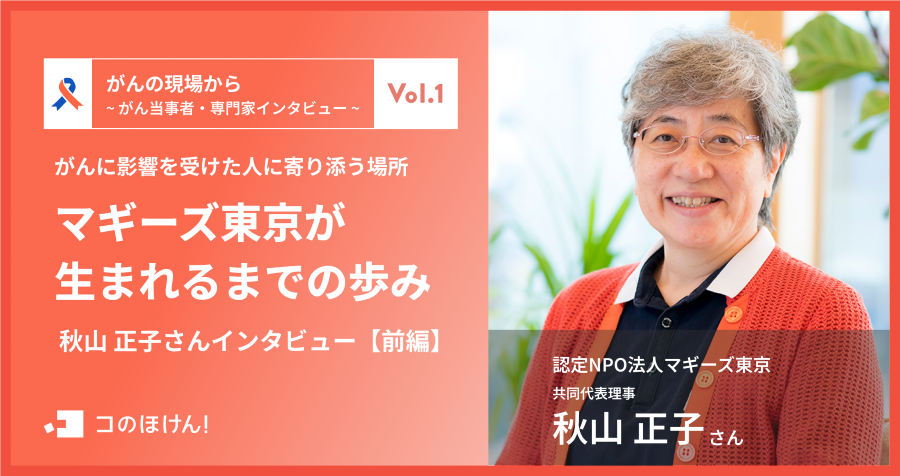
がんに影響を受けた人に寄り添う場所―マギーズ東京が生まれるまでの歩み
がんは、いまや誰にとっても特別な病気ではなくなった。しかし、本人だけでなく、家族や周囲の人々にも深い衝撃や痛みをもたらす病であることに、いっこうに変わりはない。
もし、突然がんと宣告されたとき。また、大切な人のがんに直面したとき。あるいは、がんで愛する人を失ったとき――その思いを、どこで受け止めてもらえばよいのか。
「がんに影響を受けたすべての人が、自分の力を取り戻すために」。イギリスの当初エジンバラを本部とするマギーズセンター日本第一号として、2016年に東京・豊洲に開かれたマギーズ東京は、がんの当事者だけではなく、その家族や友人から仕事でがんに関わる人まで、がんに影響を受けた人たちすべてが立ち寄ることができる場として、穏やかな時間が流れている。
今回は、認定NPO法人マギーズ東京センター長で共同代表理事を務める秋山 正子(あきやま まさこ)さんにお話を伺った。
秋山 正子さんプロフィール
- 1950年:秋田県生まれ
- 1973年:聖路加看護大学(現聖路加国際大学)を卒業。看護師・保健師・助産師として臨床及び看護教育に従事。
- 1992年:東京の医療法人春峰会の白十字訪問看護ステーションで訪問看護を開始。
- 2001年:母体法人の解散に伴い、株式会社ケアーズを起業し、代表取締役に就任。白十字訪問看護ステーション統括所長も務める。
- 2011年:東京都新宿区の戸山ハイツに「暮らしの保健室」を開設。
- 2012年:第8回ヘルシー・ソサエティ賞受賞。
- 2014年:テレビ報道記者でがん経験者の鈴木美穂氏と出会う。
- 2015年:NPO法人マギーズ東京※を設立し、鈴木氏とともに共同代表理事に就任(※のちに認定NPO法人を取得)。
- 2016年10月:東京都江東区豊洲にマギーズ東京をオープンし、センター長に就任。
- 2016年12月:ウーマン・オブ・ザ・イヤー2017 チーム賞受賞。
- 2017年:「暮らしの保健室」がグッドデザイン賞特別賞[地域づくり]受賞。
- 2019年:第47回フローレンス・ナイチンゲール記章受章。
- 2020年:第72回保健文化賞受賞。
- 2023年:朝日がん大賞受賞。
マギーズセンターとは
造園家/造園史家のマギー・K・ジェンクス氏が、乳がんの再発後に余命数ヵ月と告げられた体験から、がんとともに生きる人が「自分らしく過ごせる空間やサポート」を夫や担当看護師のローラ・リー氏(現マギーズセンターCEO)と共に模索、入院先であったエジンバラの病院敷地内に誰でも立ち寄れる場所を構想。
1995年に亡くなったあとも、その思いは受け継がれ、1996年に「マギーズセンター」が誕生。以降、イギリス全土や香港、東京、バルセロナなどに広がっている。
日本では、看護師の秋山正子氏が、共同代表理事の鈴木美穂氏とともに、2016年10月、東京・豊洲に「マギーズ東京」を開設。看護師や心理士など専門スタッフが常駐し、寄付により運営されている。

マギーズ東京の建物と空間づくり
インタビューの前に、秋山さんがマギーズ東京を案内してくれた。
マギーズ東京の敷地は約400㎡。長方形の平屋2棟が庭を挟んで並ぶ。豊かな緑が出迎える敷地入り口から向かって左が本館、右がアネックス館だ。どちらも寄付で建てられたという経緯がある。

本館は、鉄骨造のプレハブ建築であるものの、床や壁、天井にもふんだんに木が使われ、木造のような温もりがある。
入って左手には、一枚板のダイニングテーブルと大きな窓、奥にはキッチンがあり、これらのしつらいはマギーズセンターの基準に沿ったものとのこと。取材当日はマギーズ東京のスタッフがそこでWeb会議をしていた。イギリスのマギーズセンターとも定例ミーティングを行っているという。
また入口正面には、大きな本棚があった。がんに関する専門書のほか、小さな子ども向けにがんを説明した絵本も多い。秋山さんによると、子どもに自分のがんをどう伝えるか迷う親の助けになっているという。
入口右手にも来訪者のための相談スペースがある。ダイニングテーブルがあるスペースとは、ガラス壁で緩やかに仕切られ、ソファに座ると向こうの姿は見えない高さに設計されている。
またこのスペースも、マギーズセンターの本部があるイギリスのインテリアを意識しているそうだ。
ソファに置かれたクッションには、イギリスのテキスタイルデザイナーによる、落ち着いた色彩のチェック模様などのカバーがかけられている。また、ここには来訪者が率直な思いを書き残せるノートも置かれていた。
相談スペースの隣には障子で仕切ることができる半個室、さらに広めのトイレも備える。オストメイトにも対応しているほか、片隅には椅子が置かれ「ひとりで泣けるトイレ」として来訪者に安心を与える場にもなっている。


一方、アネックス館は、木材メーカーから譲り受けた建物とのことだ。入ると木の香りに包まれる室内には、かわいらしい色の椅子やテーブルが置かれたコーナーが複数ある。
秋山さんに勧められ、そのうちのひとつ、タモの一枚板のテーブルに備えつけられた椅子にクッションを抱えて腰かけると、窓越しに建物と庭が一望でき、なんともいえない心地よさを感じた。
インタビューに伺った6月は、建物のいたるところに活けられた大輪の鮮やかなアジサイが、訪れる人を迎えていた。

「最期の時間は家で」―実姉の在宅ケアから始まった歩み
秋山さん:
かつて、私は実の姉をがんで亡くしています。当時は「がん」と診断されると、入院治療がふつうで家にはなかなか帰れず、最期は病院で迎えるという時代でした。
しかし、姉は最期の時間を少しでも自宅で子ども達と一緒に過ごしたい思っていたので、私はその願いを叶えるために姉を家に連れ帰って、今の在宅ケアのはしりのようなことをやってみました。当時は在宅ケアの制度が整う前でしたが、こういったケアの形は、今後本当に必要とされると強く感じました。
その経験から訪問看護に転向し、まずは「在宅ホスピスケア」に先駆的に取り組んでいる診療所に就職し、東京都内で訪問看護の実践に取り組みました。
訪問看護を20年ほど続けるなかで、がん治療が時代とともにどんどん変わり、今あるがんの在宅療養のはしりが現れるのも目にしてきました。
一方で、がんと最後まで闘おうと治療に臨んだけれども、医師から治療の限界を告げられ次の受け入れ先を探しているがなかなか見つからない、そういった「狭間」に落ちてしまい、悲観の中にある患者さんとの出会いも何度もありました。
ご本人や家族の悔いが残らないよう、私としては頑張って訪問看護を続けても、こういった方は長くても1カ月、状態によっては伺ったその日に亡くなることもありました。
あまりに多くの方がそうやって亡くなるのを見るうちに、「本当にこういう姿でいいのか」と疑問を持つようになりました。もし、がんの治療を受ける中で在宅ケアや在宅医療について知る機会があれば、あるいは相談できる場があれば、患者さんの「生きる中身」は変わるのではないか。当時は、何ができるのだろう、どんな工夫ができるだろうと常に考えていました。

「自分の力を取り戻すケア」ーマギーズのアイディアを日本へ
秋山さん:
そんな時、2008年に日本で開催された国際がん看護セミナーで、患者さんの在宅ケアについて講演する機会がありました。
そこには、イギリス・エジンバラにあるマギーズセンター第一号のセンター長アンドリュー・アンダーソンさんもパネリストの一人として出席しており、マギーズセンターについての講演を聞きました。
アンダーソンさんへの質問の時間に「もしお金がたくさんあったら、すぐ日本にもマギーズセンターを作りたいものですね」と話したら、会場がワッと笑いに包まれたのを覚えています。
「マギーズセンターってどんな風にやっているのだろう」という気持ちが強くなっていたその3カ月後、当時ちょうどイギリスに訪問看護のスタッフが勉強に行っていたこともあり、仲間を募って2009年3月にはイギリスにあるマギーズセンターを実際に見に行きました。
実際に施設を目にすると、やっぱりすごいなと感じまして。すぐに日本ではできないかもしれないけど、マギーズセンターのアイディアだけでも日本に持ってきたいと強く思いました。その翌年2010年には、マギーズセンターCEOのローラ・リーさんの招聘講演も実現することができました。
そうした交流の中で、がんに影響を受けた方の話をじっくり聞きながら一緒に考えていく「自分の力を取り戻すケア」という、マギーズセンターの相談支援の考え方は必要だなと、改めて強く感じるようになりました。
マギーズのこころを受け継いだ「暮らしの保健室」の開設
秋山さん:
2011年には、そうしたマギーズのあり方を参考にした「暮らしの保健室」を開設しました。
場所は新宿の戸山ハイツという高齢化が進む団地の一室で、がんだけではなくそれ以外の病気や介護、暮らしにまつわるあらゆる相談も受けています。
予約はいらない、相談は無料、行けば相談に乗ってくれる人が必ずいる。さらに、来ている人同士で話すこともできる。このスタイルは、マギーズからもらったアイディアですね。
部屋の内装も木をふんだんに使うとともに、キッチンやダイニングテーブル、引き戸で仕切れる個室スペースを設けるなど、小さいながらもマギーズライクになるような工夫をしました。
ちょうどその頃、厚生労働省で在宅医療連携拠点事業というのが始まりました。そこに相談支援を地域に広げていくためのモデル事業として手を挙げたところ、全国10カ所の中のひとつとして選ばれ、事業費について助成金を受けられるようになりました。
「暮らしの保険室」は現在も続いており、最近はウクライナのある市の市長さんが視察に来ました。紛争地域から避難してきて仮設住宅の団地に暮らしている高齢の方たちが、みんな引きこもりでフレイルの状態になっている、日本ではどういう対策を行っているのか参考にしたいということで訪れたそうです。

マギーズ東京 現共同代表理事 鈴木美穂さんとの出会い
秋山さん:
はじまりは、2014年3月にウィーンで行われた「国際がん患者の集い」に、当時日本テレビの記者だった鈴木美穂さんが参加したことでした。鈴木さんはがんの当事者で(※編集部注:鈴木さんは2008年に24歳で乳がんと診断された)「がんの相談や家族のケアもできる場所を作りたい」という思いをそこで話したところ、参加していたヨーロッパの人から、イギリスのマギーズセンターを紹介されたそうです。
それで、マギーズセンターのホームページを見てみたらとても素晴らしい内容だったと。そこで、さらに興味を持って「マギーズセンター ジャパン」で検索してみたところ、私が以前書いていた文章が数件出てくるだけだったそうです。
じゃあ、その「秋山正子」という人はどういう人で、何をしているのかと調べていったら、私の開設した「暮らしの保健室」にたどり着いたそうです。
同年4月には鈴木さんが「暮らしの保健室」に記者として取材に来てくれました。「暮らしの保健室」は整えられた空間の中リラックスして相談ができ、様々な人が行きかう場でもあります。バックには訪問看護ステーションがついているという体制も珍しく、これからの地域包括ケアの要(かなめ)やハブとしての役目を担っていく施設として、日本テレビのニュースに取り上げてもらいました。
%20(1).jpg?w=700&h=468)
ふたりの想いで動き出した「マギーズ東京」
秋山さん:
そうして取材に来た鈴木さんは、ウィーンで聞いたマギーズセンターについて調べてみたら、「暮らしの保健室」にたどり着いたという話をしてくれました。また、ご自身もがんの当事者で、日本でマギーズセンターのような施設を作りたいという話も。
それで私から「じゃあマギーズセンターを、日本でもぜひ一緒にやりましょう」と声をかけ、2014年の4月には「マギーズ東京プロジェクト」を立ち上げました。鈴木さんが立ち上げた団体のメンバーと、私たちのグループのメンバーが半々で、NPO法人としての申請も行いました。
ちなみに、マギーズセンター東京が建つこの豊洲の土地は、不動産会社に勤める鈴木さんの大学の同級生の方から紹介してくれたものです。当時は豊洲市場が開く前で、一面草ぼうぼうの更地でしたが、東京オリンピック終了の期間まで、健康・スポーツ・アート関連の事業計画がある人達に安く貸すことができるという話でした。
その申請の締め切り直前に一緒に事業計画を練って、その方が会社に提出してくれたところ、2014年5月にはこの土地の一部の使用が認められたというストーリーがあります。
インタビュー後編に続く
その後、秋山さんは鈴木さんとともに2015年4月には「NPO法人マギーズ東京」を設立、2016年の10月にはこの豊洲の土地にマギーズ東京をオープンさせた。オープン以来、豊富なグループプログラムなどによりがんの相談支援の輪を広げ続け、2025年7月時点で延べ利用者数が4万8,474人を超えた。
マギーズ東京への運営は寄付金によりすべて賄われているが、施設の理念に共感するサポーターは法人・個人問わず増え続け、今では地方でマギーズセンターの開設を志し、奮闘するボランティアも多く現れている。
インタビュー後編では、マギーズ東京で相談支援活動を行う中で、秋山さんの印象に残った出来事や、それを通じて考えたがんに影響を受ける人の「生きる尊厳」とは何かについてお伝えする。